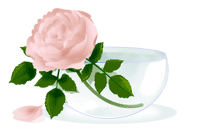
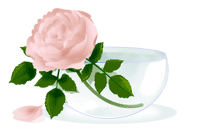
2
|
扉の色が青を示すと、鴎の声と共に正午の光と潮風が室内へと流れ込む。
ハウルは美しい金色の髪に海の香りを漂わせ、彼は乱れの無い ・ ・ ・それでいて少しだけ早めの歩みを進め、小走りに短い階段を登り真っ直ぐと二階へと向かった。 肩にかけたままだったキングズベリーの国旗を思わせる色合いの薄紅と黄金柄の上着を脱ぎ、ソファーに無造作に掛け ・ ・ ・そのまま台所へと進み、先ほど購入した茶葉をおき、水場の近くにある食材をいくつか手に取り選定しつつ、暖炉で薪を抱えているカルシファーへと声をかける。 ・ ・ ・その際も彼は手を止めてはいない。 「カルシファー、ソフィーは?」 「さっき起きてきてみんなに朝食作ってた」 「はあ!?」 器用にペティナイフで芋の皮向きを進めていた手を止め、彼は目を見開き驚愕し、そらされることのなかった視線が芋からカルシファーへとすり返られる。 そんなハウルの反応に思わずカルシファーは肩をすくめてみせた。 ・ ・ ・炎であるのに”肩をすくめる” ・ ・ ・というのも、いささか妙な表現ではあるが。 「お、オイラを怒らないでくれよ!オイラだって止めたんだぜ?顔色悪いんだから大人しく寝てろってさ ・ ・ ・マルクルだって」 「 ・ ・ ・はぁ ・ ・ ・」 彼が嘘を吐くとは思えない。 ・ ・ ・吐く必要もない。 それに今のカルシファーの弁解は実に説得力のあるものであり、それはこの家族の中においてはソフィーを一番理解している ・ ・ ・つもり、であるハウル自身も痛いほどに分かっていることだ。 ハウルは視線を空(くう)へとあげて脱力するようにため息を吐く。 そして小鳥が囁くほどの声色で独り言のように ・ ・ ・ 「やっぱり昨夜、具合悪かったんだ。 ・ ・ ・それならそう言ってくれれば僕だって」 とぼやいた声を悪魔のカルシファーは聞き逃さなかった。 ・ ・ ・元々物質以外の音すら聞き分ける聴力を持つ彼であること、聞き耳を立てずとも嫌でも入ってきてしまったのではあろうが。 「何ぶつぶつ言ってるんだよ」 「こちらのことさ」 先ほどまでの脱力感は何処へ言ってしまったのやら、カルシファーからの指摘を受けた途端、彼は、実に自然な仕草で背筋を元の形のよいものへと戻しつつ、にこ、と目を細めて優雅に笑ってみせる。 ・ ・ ・ソフィーが表現するところの、”大人の笑み” ・ ・ ・というやつだ。 そして彼は気を取り直して、また手際よく芋の皮向きを再開するのだ。 この手際の良さを見れば王宮の魔法使いとしてどころか、調理師としてのオファーすら来そうなほどに素早い動作だ。 伊達に長年、独りで生計を立ててきたわけではない。 「ソフィー、何か食べていた?」 「食欲が無いって言って、あっためた牛乳をちょっと飲んでた」 「 ・ ・ ・そんなに辛いのかい?」 「歩くのもやっと、って感じだったぜ」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・おっかしいなぁ ・ ・ ・そんなはずは ・ ・ ・」 ・ ・ ・と、またもや独りそっと呟く声にカルシファーが、 「 ・ ・ ・だから、何をぶつぶつ言ってるんだよさっきから」 と聞いてはみるものの、 「こちらのことさ」 ・ ・ ・と、やはり微笑の再放送で会話は勝手に自己完結される。 ソフィーと再会を果たしてからというもの、ハウルは目を見張るまでに男として、人間として成長したものだが ・ ・ ・、 ・ ・ ・正直、根本的な部分は何一つ変わってはいないのだ。 ・ ・ ・ま、別にいいけど ・ ・ ・とカルシファーは口のあたりでくすぶった煙を出して見せた。 ・ ・ ・所謂人間でいうため息、というやつだろう。 この会話はもはや終わったも同然だ、とカルシファーは話題を変えた。 こちらも時間の問題ではあろうが。 「そうそう、マルクルが花をお客んとこに届けに行くからって、ばあちゃんもついでに昼食さっきとってたぜ」 「知ってる。洗い場に2人分のお土産が置いてあったからね」 ってことは結局2人分の昼食もソフィーが用意したんだね、とため息まじりに囁く。 お土産、という表現は彼なりの冗談か、正直な皮肉なのだろうか。 いずれにせよ、ハウルはそれを知っていたゆえ、こうして2人分の材料にしか手を付けなかったのだろう。 ・ ・ ・そうこうしている間にも、もはや下ごしらえは終了し、彼は厚めの片手鍋をカルシファーの頭上へ何の躊躇いも無しに押し付ける。 ・ ・ ・いつものことだが。 「早めに帰ってきて良かった。あのばあちゃんとソフィーと君だけなんて危険すぎる」 「おいおい、オイラを信用してくれよ」 「信用してるさ。だから危険なんだ。 ・ ・ ・君は筋金入りのお人よしだからね」 「褒めてるんだかけなしてるんだか ・ ・ ・」 「敬っているのさ」 「どこがだよ」 それにこうしてハウルの苛立ちのさりげないはけ口へとされるのもまた、カルシファーにとっては日常茶飯事のことなのだ。 「あのさ、あんまりソフィーを叱るなよ」 「 ・ ・ ・君までそんなことを言うんだね」 唐突な悪魔の言葉に、ハウルは苦笑する。 ・ ・ ・失笑にも思える笑い方だ。 「何だよ、誰に言われたんだ」 「茶葉屋のおばさんに」 「どうして」 「さあ? ・ ・ ・ねえ、僕ってそんなに怖く見えるかい?」 「さあなぁ ・ ・ ・オイラ、人間の感覚ってよく分からないや」 「 ・ ・ ・それもそうだね。確かにそうだ」 そしていつものパターンは、こうして鬱憤を気付かれぬようにはけだすハウルは、はけだしていくほどに沈んでいくのだ。 ・ ・ ・その理由は分からないが。 案外、この魔法使いはその繊細さ故、肝心なことに関しては突如としてネガティブになりやすい性質のようである。 今度はカルシファーの方が会話を勝手に自己完結させた。 ・ ・ ・このまま続けて、もし万が一また闇の聖霊でも呼び出された日には叶わない。 「ところで、何を作ってるんだよ?」 「ん? ・ ・ ・んー ・ ・ ・この前ソフィーがマルクルの好き嫌い対策に作ったスープ」 「レシピ聞いたのか?」 「勘さ」 彼が心臓を失ったとき ・ ・ ・同時に味覚をも失った。 子供の頃は必死に何かを、少しでも美味しいと感じられるようになろうと必死に様々な料理を覚えていた彼だが ・ ・ ・いつしか、諦めたように簡単な料理しかしなくなったのだ。一日に必要な栄養だけをそのまま食事にしたようなものだ。 故に、あまり食卓に暖かい料理が並ぶことが無かったのだろう。 彼の料理の巧みさは、子供時代に培われたものなのだ。 ハウルにとってはソフィーの作った暖かな食事が、初めて”美味しい”という感覚を教えてくれるものとなったのだろう。 そのためか、彼はよく彼女が炊事場に立つと、決まって自分も横に立つ。 失い、取り戻したものの大きさを自らに言い聞かせるかのように。 ・ ・ ・ああ。 カルシファーは正直者だから、きっとハウルにみんな喋ってしまったんだわ。 ハウルの言いつけを破って家事をしただんて聞いたら、いくら優しいあのひとでもきっと怒るに違いが無い ・ ・ ・ああ、どうしよう。 怒られるだなんて ・ ・ ・、どうしよう、どうしよう、どうしよう。 ・ ・ ・と。 ソフィーはハウルの自室のベッドに埋もれるように小さく丸まって、不安に大きく震える自身の心臓を必死に押さえ込んだ。 目覚めてすぐに具合が悪いのだということをハウルに見抜かれて、その際彼は優しく検温してくれたり、家事は今日はしないこと、と指きりまでしてくれたというのに。 そうだ。 これはきっと、長女の性だ。 何があろうが張ってでも仕事と家事をこなさなければと自らを無理やり奮い立たせるのは、きっとこの長女という自身の運命によるものだ ・ ・ ・ などと、こじつけのようにソフィーは全てを長女、というもののせいにした。 せいにして ・ ・ ・皮肉なことに、空しくなったのもまた事実である。 ・ ・ ・そして。 ノックの音に、ソフィーは飛び上がる。 慌てて毛布を頭まで被り ・ ・ ・これではまるで、拗ねた子供である。 扉が開く音がすると同時に ・ ・ ・彼の、吐息を漏らす音がして。 呆れられた? ・ ・ ・と不安になるが。 その吐息は呆れではなく、笑みがこめられたものだった。 心底楽しんでいるような含み笑いだ。 ソフィーはますます顔を出すことができなくなってしまった。 すると、まるで悪戯っ子のような若々しい声が毛布越しに降りてきた。 「かくれんぼかい?楽しそうだね。鬼は誰?」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 ・ ・ ・、 ・ ・ ・なんと、いうか。 実にハウルらしい表現方法であるが ・ ・ ・それは最大級の皮肉にすら聞こえた。 完全にソフィーの思い込みではあるが。 頑なに口を閉ざす彼女に、ハウルは ・ ・ ・恐らく顔が隠れているであろう部分の毛布に唇を寄せ、そっと囁く。 「もう、いいかい?」 「―――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・っ」 突然の至近距離からの温もりにソフィーは驚き、身を固くさせる。 そんな彼女に構わず。 「もう、いいね」 「あっ!」 ハウルは卒の無い動作で毛布を取り払う。 そこには油断していたためか、身体を丸くさせたままのソフィーがあった。 ある意味、実に情けない姿を晒してしまったこととなる。 顔を高揚させるソフィーと、優しく優雅に笑うハウル。 いくらなんでも酷い ・ ・ ・と彼女が抗議する前に腕を引っ張りあげられ、そのまま腕の中へと拘束される形に収まってしまう。 形の良い口元は、首筋に。 こんなことをされると ・ ・ ・もはや、彼女には発言権など無いに等しい。 卑怯な、禁じ手である。 どうやらハウルにその自覚は無いらしいのだが ・ ・ ・。 その、卑怯な美貌の魔法使いは無邪気に大人の顔を覗かせる子供だ。 「わからず屋のソフィー、ベッドに入っていなさいって約束を破ったね?」 「 ・ ・ ・」 「指きりまでしたのにね」 けれど、非がソフィーにあることもまた事実で。 「 ・ ・ ・ごめんなさい ・ ・ ・」 「針千本飲ますって、言ったよね?」 そういえばソフィーは針子でもあるから、針は沢山持ってるよね ・ ・ ・なんぞという聞き捨てならないことまで口走るが ・ ・ ・恐らく本気ではない。 本気だと、それこそ噂どおりの魔法使いハウルそのものとなってしまうではないか。 ソフィーはハラハラしつつ、ハウルの顔色を伺いながら、必死に弁明の機会を伺うのだが ・ ・ ・浮かんでくるのは回りくどい言い訳などではなく、彼に対する素直な謝罪の言葉の候補ばかりであった。 「本当に ・ ・ ・ごめんなさい ・ ・ ・」 彼はいつもどおりに優しくしてくれるが、その仕草や声の響き、瞳のわずかな蠢きでソフィーはいち早くハウルの異変を悟った。 ・ ・ ・怒っているようではないということもすぐに分かった。 手の優しさは、自分を責めるものではなくて ・ ・ ・ むしろ、自分に縋っているような感覚すら覚えたのだから。 とはいえ、この会話上、”どうかしたの”などとソフィーが問うのは非常に妙である。 どうしたの、の”どうした”の大半はソフィーが原因であることに違いはないのだから。 ・ ・ ・つまりハウルは自分に関係することでわずかな変化を除かせている、それも彼を追い詰めるような形で ・ ・ ・とは、察してはいるのだが。 ソフィーはあれやこれやと具合の悪い状態を押して色々と思案するがやはり合点のいくような都合の良い言葉は見つからない。 そんな、彼女の身体を。 「!」 「 ・ ・ ・ソフィー」 ハウルは、蛇のように抱きしめて。 「してもいい?」 「 ・ ・ ・え?」 「キス」 ・ ・ ・不思議と。 この時に限って、ソフィーは動揺しなかった。 心のどこかで、本当に不思議な事に、ハウルはそう言ってくるのではないか ・ ・ ・と予感していたからなのかもしれない。 最近の彼のキスは、無邪気ゆえのそれではなく ・ ・ ・どこか。 どこか ・ ・ ・苦しげで。 「 ・ ・ ・、 ・ ・ ・いいわよ」 「 ・ ・ ・ありがとう」 同意を得たその表情も、その微笑も ・ ・ ・どこか、頼りなく。 ・ ・ ・不安、なのかしら ・ ・ ・、とソフィーは思った。 彼とのキスでここまで冷静でいられる自分は初めてだった。 こうして唇を受け止めて、ようやく分かることだってあるのだ ・ ・ ・と、ソフィーは昨夜に彼とのそれで知ったのだ。 いけないことでも、咎められるようなことでも、決して無い。 重ねられた唇が離れると ・ ・ ・ソフィーは笑った。 先ほどまでのベッドの中で情けなく丸まって震えていた少女はもはやいない。 いつもの、二本の足でしっかりと立つ、18歳の妻である。 「美味しそうな匂いがするわ」 「 ・ ・ ・え?」 「お昼ご飯作ってくれたのね」 「 ・ ・ ・うん」 「ありがとう。ハウル、大好き」 深刻な問題ではなさそうだ。 ハウルは最近、いささか情緒不安定な顔を覗かせる。 心臓が戻ったことによる副作用なのかもしれない。 今まで素通りできたことができなくなり、容易かったことが難しくなった。 気付かなかった膨大な情報が彼の心と思考を襲い、許容範囲を超えてしまうのも自然のことだろう。 ・ ・ ・心のどこかで気付いていたことだが。 でも。 こうして本当の気持ちをぶつけることで、ハウルは笑ってくれる。 作り物ではない、本物の笑顔を真っ直ぐに向けてくれる。 だからソフィーは常に素直に、真っ直ぐに彼へとぶつかっていくことに決めたのだ。 ・ ・ ・だから、昨夜はハウルの願いを少しだけ、自分の出来る限りであるため本当に少しではあるが ・ ・ ・叶えてみせたのだ。 それはほんの些細なことではあるが ・ ・ ・改めて恋人であること、彼の妻であることを強く自覚するきっかけにもなった。 これから、まっさらな同士、手探りで知っていくのだろう。 恋人としてするべきこと。 夫婦としてするべきことを。 そのためには ・ ・ ・ わたしが、ハウルを守ってあげなければ。 甘やかすのではない。 過保護になるのではない。 守るということは、きっとそんなことではない。 彼を独りの男性として、受け止めること。 その背負っていた運命も、それを降ろしたことによる副作用も。 わたしの、心と、身体を賭して。 ・ ・ ・ここまで言ってしまうと、大袈裟だが。 ふと、これがよく世に出る小説にある、”尽くす歓び” ・ ・ ・とやらなのだろうか ・ ・ ・と。 ソフィーはハウルに抱き起こされながら、そのようなことを考えていた。 |
20050602
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
