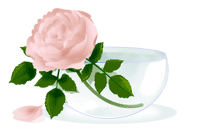
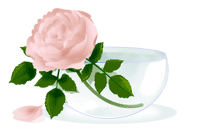
1
|
港町の賑わいは、一時期の気の毒なほどの静寂からはようやく回復したようだ。
戦争は未だに終わる様子が無いが―――空襲の回数は確実に減り、人々はそれを見かねて住み慣れた街へと戻り、再び活気を取り戻そうとその腕を奮っている。 その努力の甲斐あって、今ではこうして元通りに近い状況だ。 戦時中ということもあり、食料を大量に買い込む中年女性が通常よりも多く見られ、軍人は軍人でつかの間の休息にありつこうと昼間から酒場に繰り出している。 故に、お世辞にも治安はよろしいとは言えない。 そんな喧騒にも近い賑わいの中。 この場の空気とは明らかにかけ離れた青年が、茶葉屋の前に颯爽と立っている。 すらりと伸びた高い背に、一件華奢にみえるその体。 さらりとした金髪が白く繊細な肌の上を滑り、エメラルドのピアスを揺らす。 地球を思わせる蒼の瞳は、じっと香り立つ茶葉へと向けられている。 その姿に、荷物を抱え込んだ女性も、買い物を終えた少女も、皆立ち止まる。 その茶場屋は、正直、この付近でも評判とは言い難い店である。 今では大手の雑貨屋や食料店が安く茶葉を販売している為、昔ながらのこういった専門店は軒並み潰れてしまい今ではもはや見る影もない。 唯一生き残ったこの店も、時間の問題であろう ・ ・ ・と誰もが予想していた。 そんな、閑古鳥の鳴っていた店に。 「すみません、ご店主はいらっしゃいますか?」 ・ ・ ・等と、まるで王国の騎士か貴族の紳士であるかのような、優雅で若々しい青年の声が響くのは――― ・ ・ ・恐らくは創業以来初めてのことであるに違いは無い。 久々に聞いた客の呼ぶ声に、店主 ・ ・ ・初老の男性は奥から慌てて顔を出した。 そして ・ ・ ・その客が誰であるかを確かめるよりも、己の店の前に見たこともないような人だかりが出来ており、尚且つそれらがこの店を取り囲んでいることを知ってたいそう驚いたようだ。 ・ ・ ・が、そこはさすがに長年客商売を一筋に生業としていた彼であること、気持ちを取り直して客の応対へと思考を切り替え――― ・ ・ ・た、のだが。 ・ ・ ・店主は、口をぽかんと開けたまましばらく立ちつくすこととなる。 ・ ・ ・と。 「ちょっとあんた、何をぼさっとしてるんだい!お客さんだよ、何をつったって ・ ・ ・」 騒ぎを聞きつけた妻が同じく奥からずかずかと店へと顔を出し ・ ・ ・その意味を知る。 本来であれば亭主をしかりつけていつものように客の対応を自分がしてのけるつもりだった―――はずであるのに。 その、青年は。 いささか、美しすぎたのだ。 妻も、やはりしばらく立ち尽くすが。 さすがは港町に生きる女性、気丈な態度で応対を始めた。 この程度でのらりくらりとしていられるほど、現状は芳しくはないからだ。 現実というものが、今の彼女をここまで働かせるのだろう。 「いらっしゃい。 ・ ・ ・何かお探し?」 おまけに、いくら美青年でも、もし冷やかしであれば罵声の一つでも浴びせて帰らせるくらいの気持ちであったのだ。 何故彼女をここまでにするか ・ ・ ・それはこの港町に最近になってあふれ出した、昼間から酒びたりになって街を徘徊する軍人達を嫌というほど見てきたからだ。 最初はさすがに恐怖を感じたものの、今では満面の笑みで兵士を追い払うまでに成長した。 ・ ・ ・とにかく、愛する亭主とこの店を守るために彼女は必死なのだ。 そんな、初老の女性に。 青年は、嫌味の無い、素直な微笑を見せた。 優しさと慈愛に溢れた瞳だ。 「ええ、紅茶がきれたので。我が家はこの店の茶葉だと決まってるんです」 「――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 その、言葉に。 常連がいないに等しい彼女は首を傾げると同時に、現実離れした美青年が発した”我が家”という言葉に ・ ・ ・なによりその優しい眼差しに、頑なになることを止めた。 この青年は、良い客だ。 長年の勘が、そう思わせたのかもしれない。 「そうかい、ありがとうね!しがない店だけど、茶葉なら何処にも負けないんだよ」 素直な笑みを浮かべながら、ああ、このひとだかりはこの青年によるものかね、と察し、未だにぽかんとしている亭主の尻をはたく。 そして再び視線を青年へと戻した時には、彼はこちらへと一切れのメモを差し出しているでは無いか。――彼女はきょとんと小首をかしげ、それを受け取る。 広げてみると ・ ・ ・そこには茶葉の種類とブレンドなどの説明が書かれていた。 ・ ・ ・なるほど、見ない顔だと思ったら常連さんの親類か ・ ・ ・と半ば彼女は納得し、 「ああ、これね。これはちょっとお薦めなんだよ」 と、メモどおりに茶葉を選び、秤に置く。 ・ ・ ・その作業をしながらも、 ・ ・ ・このブレンドは確か ・ ・ ・とあることに気付くのだ。 その事実に、思わず茶葉をこぼしそうになったが、 ・ ・ ・どうにかそれを止め。 自然と、こんなことを口にしていた。 「もしかして ・ ・ ・お客さん、ソフィーさんの知り合いかい?」 「え?」 突然の言葉に、さすがに青年もわずかに驚いたようで眼を少しだけ見開く。 しかし彼女はそれに構わず話をつらつらと続けていく。 ・ ・ ・どうやら、大分この青年の美貌に慣れてきたようだ。 「うちの常連さんっていったら、ソフィーさん一人だからねぇ ・ ・ ・つい最近初めて顔を出してくれた子なんだけど ・ ・ ・あの子よく軍人に絡まれててねえ」 「 ・ ・ ・」 「あの子ってね、自分じゃ気付いていないんだろうけど ・ ・ ・そりゃあ可愛い良い子でね。それに年頃だし ・ ・ ・とてもじゃないけど、今の港町(ここ)で独り買い物なんてさせちゃあ危ないと思ってね ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・」 ソフィーという少女は、実に不思議な少女だ。 髪は見たことも無い白銀で、それは夜空に光る星を思わせる。 けれどその反面、瞳は大地の優しい色で、実に深い慈愛に溢れている。 折れてしまいそうなほど華奢な体つきで、実年齢より幼く見える笑顔は ・ ・ ・まるで戦争で死別した独り娘の年頃の頃を思い出させて ・ ・ ・他人のようには思えなかったのだ。それで色々と勝手に世話を焼いているんだよ ・ ・ ・と青年に苦笑しながらも言いつつ ・ ・ ・その時には茶葉はしっかりと袋詰めされ、精算も済ませていた。 「はい、ありがとう」 勝手なことをべらべら喋ってしまってごめんなさいね、と彼女は言いながらも ・ ・ ・ やがて、ソフィーと彼との関連が無いのではないか、と思い始める。 ああ、しまった、人の私生活を勝手に ・ ・ ・とにわかに焦りはじめたとき。 「 ・ ・ ・ありがとう」 「 ・ ・ ・えっ?」 思わぬ、礼を言われて驚かされる。 茶葉に対するありがとうなのか、それとも別のことに対するものなのか ・ ・ ・ 考えを巡らせていると。 青年は瞳を細めて微笑んだ。 その際にゆれた金髪が、さらりと首筋を滑る。 ・ ・ ・花の香りがした。 ・ ・ ・と、思っていたら。 「妻が、お世話になったようで」 ――――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・。 一瞬、彼女の頭の中が真っ白になった。 また、この美青年からは似つかわしくない”妻”という言葉を聴いたからか。 ・ ・ ・いやいや、そうではない。 そうではなくて――― ・ ・ ・ 「本当なら今日も妻が来る予定だったのですが ・ ・ ・少し体調が優れなくて ・ ・ ・、今日は僕が代わりに」 なんというか。 「でも、今日は来れて良かった。いろんな話が聞けましたしね」 安心、したのだ。 「港町では気をつけるように、言って聞かせます」 ソフィーは茶葉を選ぶ際、決まって顔を赤らめることがある。 小気味良く茶葉を選ぶ指先が ・ ・ ・ある茶葉を選ぶときになって少しだけ止まるのだ。どうしたのかと顔を覗いてみれば、彼女は頬を赤らめて ・ ・ ・はにかんでいた。 明らかに、恋をする女の顔だった。 確実に短い付き合いではあるが、娘のように感じていた彼女が、一体どこの馬の骨とも知らない男に心を奪われたのか ・ ・ ・とハラハラしていたものだが ・ ・ ・。 ・ ・ ・なるほど。 この青年か。 彼女と同じ、花の香りがする ・ ・ ・この美しい青年がその相手か。 それでもやはり、どこか寂しさは隠しきれず、苦笑いのようになってしまったが ・ ・ ・ 彼女は、微笑んで言ってみせた。 「あまり、叱らないでやってね」 「心得ています。 ・ ・ ・それに、寝込んでいる彼女にきつくなんてできませんよ」 「ふふふ ・ ・ ・確かにそうだね ・ ・ ・、 ・ ・ ・ああっと ・ ・ ・そういえば、ソフィーさん体調悪いって ・ ・ ・風邪か何かかい?」 「いえ ・ ・ ・そういうことではなくて ・ ・ ・。 ・ ・ ・大丈夫です。熱もないですし」 その質問には、何故か青年の流暢な言葉は突如としてわずかに歯切れの悪いものとなる。気のせいかもしれないが、かすかに視線が泳いだことを ・ ・ ・この初老の女性は見逃さなかった。 ・ ・ ・かといって、責め立てるつもりはさらさら無いが。 そんな野暮なことはいう気もないし、酷いことではないとも分かっている。 何故なら、この青年の微笑が崩れていないからだ。 ・ ・ ・が。 ふと、街の時計台が午前11時を知らせる。 その鐘の音を聞き ・ ・ ・青年は顔を上げた。 「 ・ ・ ・いけない、こんな時間だ」 「おや、まだ昼前だけど急用かい?」 「ソフィー、朝食を取っていないので ・ ・ ・そろそろ昼食を作ってあげないと」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・あんたがかい?」 「ええ。家事は分担するって決めているんです」 「 ・ ・ ・できるのかい?」 「大丈夫ですよ。僕とて、結婚前は自炊してましたから」 苦笑して。 ありがとう、今度はふたりで来ます――― ・ ・ ・と流れるように言い残し。 青年は、その場を去った。 そうして、しばらくその背中を見送った後。 彼女は、ふつふつと笑いがこみ上げて仕方が無くなってしまった。 懸命に我慢していたのだが ・ ・ ・どうやら限界のようだ。 ああ、駄目だ、お客様のことを笑いのネタにするなんて ・ ・ ・と自らに言い聞かせても、どうやら無理なようだ。 しまいには、声を上げて笑い出してしまった。 そんな妻をみた店主は、ようやく正気を取り戻したのか、そんなおかしな笑い方をする彼女を心配し、恐る恐るといったようにそっと声をかける。 「おいおい、どうしたんだよ。 ・ ・ ・気でもふれたのか?」 「あはははっ、はははっ ・ ・ ・、 ・ ・ ・ああ、いや、そうじゃないんだよ ・ ・ ・、 ・ ・ ・ふふふっ」 「じゃあ、なんだっていうんだよ」 「間抜けに口をあけっぴろげにしたまま突っ立ってたあんたに言われたか無いねぇ」 ・ ・ ・それを言われてしまっては、身もふたもないではないか。 亭主は機嫌をそこね、奥へと戻っていってしまった。 けれど、大丈夫だ。 あの男は一杯でも酒を飲ませれば、けろりとしてみせるのだから。 長い長い夫婦生活の元に知り尽くした夫のことだ。 自分が一番、良く分かっていると思う。 そうで、ありたいと願っている。 この時代においても、夫は浮気一つせず、博打にも手を出さず、ひたすら懸命に自分と店を守ってきてくれた。 だから自分もそうするのだ。 だから自分も、夫とこの店を守るのだ。 あの青年も、そうなのだ。 まさしく、そうなのだ。 一見、あまりにも美しく、さすがの自分も言葉を失うほどに驚かされてしまったが。 ・ ・ ・けれど、妻 ・ ・ ・、ソフィーの話をした途端 ・ ・ ・どうだろう。 あの美貌が、わずかに幼く感じられたのだ。 やけに”妻”であることを強調した言葉を使ったのも、背後の人だかりに紛れていた軍人達に聞こえるような声色だったということも、彼女は聞き逃さなかった。 あの美貌の青年は、心底ソフィーに惚れているらしい。 ・ ・ ・だから夫となったのだろうけれど。 それを思うと、本当に本当におかしくて。 ああ、やっぱり男なんて生き物は、どんなにえばってみせたところで ・ ・ ・所詮は女の腹から生み出されたもの。人にはよるが ・ ・ ・、いや、それにしても。 ああ、おかしい。 おかしくておかしくて ・ ・ ・笑いが止まらない。 ああ、違う、これはきっと ・ ・ ・ソフィーが幸せだと知った安心からに違いない。 彼女がいつも独りで肩身を狭そうに港町を歩いていたのは、軍人を警戒してのことだったのだろう。けれどそうしてでも港町にやってくるのは ・ ・ ・ 「 ・ ・ ・あんた!うちの店も、まだまだ捨てたもんじゃあないみたいだよ!」 「何をまだヘラヘラとしているんだ。こっちも昼飯にしてくれ!」 「はいはい、その前にあんたには一杯酒を飲ませないとね」 それで、しばらくはダラダラとしていてもいいさ。 後は私が店番をしてやるよ。 今日は、めずらしくあんたに親切にしてやりたい気分なのさ。 そうして彼女は、今ソフィーがあの青年にどんな看病をされているのかを想像するのだ。そうして、やっぱり少しだけ噴出してしまう。 どう考えても、やっぱりあの青年の、あの幼い表情ばかり浮かんでしまうのだから。 老婦人は笑いながら、店先に”準備中”というプレートを下げ、そっと奥へと戻っていった。人だかりなんて知ったことではない。元来野次馬など好きではないのだ。 しかし、これを期にこの店が繁盛し始めるのだが――― それは、まだ少しだけ先の話。 |
20050602
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
