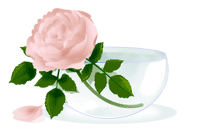
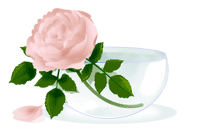
10
|
法律というものは、時として勝手で残酷なものだ。
”魔女狩り”が施行された途端、婦人の外出禁止の法令は廃止となった。 その理由は説明されずとも、ソフィーには分かった。 外に人が出なければ、魔法使いは見つからない。 皆、金銭や食料目当てで魔法使い狩りを始めたとも聞いている。 国は、民を利用している。 その事実だけは、誰もが察していた。 だが、国は戦争により全てを吸い上げられ、一般市民は生活苦を強いられている。利用されていると知った上で、彼らもまた国を利用する他生きる術が無いのだ。 ソフィーは夫であるハウルが魔法使いとしては国から独立し、国際的な機関である連合に属しているため、また、彼が独立するだけの経済力を有しているため苦労などしてはいないが ・ ・ ・ 花屋という職業上、この国の状態が痛いほど伝わってくる。 花屋を始めたばかりの頃、まだ国はその影を晒してはいなかった。 売れる花は、皆華やかなものばかりだった。 手にする女性達の笑顔は、それに負けないほどに明るいものだった。 ・ ・ ・けれど。 今、売れている花は――――白い百合。 それも、以前より売り上げは伸びている。 ・ ・ ・異常なまでに。 そして今、漆黒のドレスを身に纏った婦人が一人、白百合を買いに来た。 子連れなのだろう。店の外には黒い服を身に纏った年端もいかない幼い少女と少年が俯きながら立っている。 良く見れば婦人の纏うドレスは綻びだらけで、微かに汚れていた。 空襲で家を焼かれたのだろうか。それともずっと、国中を彷徨っていたのだろうか。 それにも関わらず、彼女が花を買いにきた理由は―――只、一つだ。 ・ ・ ・ソフィーは、それを知っていたから。 両手いっぱいの白百合を、婦人へと渡したのだ。 沢山の白百合を手渡された婦人は、呆然とソフィーを見た。 花を買うために用意していた紙幣を握り締めたまま。 それに、ソフィーは微かに笑って見せた。 ・ ・ ・笑わなければ ・ ・ ・、そう自分に言い聞かせてのことだった。 「 ・ ・ ・どうして ・ ・ ・?」 呆然と放たれた婦人の声は、痛々しいまでに枯れていた。 ・ ・ ・水に飢えているのか。 ・ ・ ・それとも ・ ・ ・泣き続けていたのだろうか。 婦人がソフィーに問うた理由は、渡すはずだった紙幣では到底買えないほどの白百合の数に驚いたからなのだろう。 この時代、どの店もどの家も、決して余裕などないはずなのだ。 空襲の酷かった市街地においては、パン一切れを相場の数倍以上で売りさばいている子供すらいるのだ。 ・ ・ ・それなのに。 そう、言葉にはせずも瞳で尋ねる女性に、ソフィーは言った。 信じられないほどに、優しく強い声だった。 「 ・ ・ ・お店、今日でおしまいなんです」 「 ・ ・ ・え?」 けれど ・ ・ ・どこか、儚く。 「このまま残していても、枯らしてしまうだけですから」 「 ・ ・ ・」 そして、脆く。 「あなたに、差し上げます」 「 ・ ・ ・でも」 「街のすぐ南方には、花屋がありません。そこには大きな墓地があるんです。お墓に入るひとは沢山いるのに、墓石を作るひともお花を売るひとも、皆戦争に取られてしまっていないんです」 「 ・ ・ ・え ・ ・ ・?」 それは―――― ・ ・ ・覚悟にも、似た。 「私は南方にはいけません。すぐにここを発ちます。だから、どうかそのお花を南のひと達に売ってあげて下さい」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・」 「きっと、待っています」 「 ・ ・ ・、あ ・ ・ ・」 危うげな、笑顔。 ・ ・ ・本来であれば、この申し出は断るべきなのだろう。 だがこの女性には、断るほどの余裕はもはや無い。 幼い我が子のために、明日すら知らぬやもしれない命を絶やすわけにはいかない。 その為には――― きっと、彼女はあらゆるものを犠牲にするだろう。 他人も。 ・ ・ ・そして、自分すらも。 「 ・ ・ ・感謝します ・ ・ ・」 婦人は腕一杯の白百合をそっと抱きしめ、念じるように瞳を閉ざす。 そして未練も無く踵を返し、店を出ようと、真っ直ぐと歩み ・ ・ ・ドアノブに手を掛けたとき。―――送り届けるように共に歩みよったソフィーが、そっとその痩せ細った黒衣の背中へ語りかけた。 「 ・ ・ ・宛は、あるのですか?」 「 ・ ・ ・ええ。 ・ ・ ・私の実家が隣町にあるのでそこへ ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・」 ソフィーは、瞳を伏せた。 ・ ・ ・隣町は最も空襲が酷かったとハウルから聞いていたからだ。 あそこはまだ手付かずで、復興の兆しすら見えていないという。 ぎゅっと、自らの衣服の胸を頼りなく掴む。 ・ ・ ・この婦人には、もはや宛が無いも同然なのだ。 ・ ・ ・が。 「 ・ ・ ・大丈夫ですわ、お嬢さん」 「えっ ・ ・ ・?」 ふいに振り向いた婦人の瞳は、妙に強い意思に光って見えて。 ・ ・ ・ソフィーは、背中に冷たい何かが駆け抜ける感覚を覚える。 あと少しで、半歩ほど後ろに下がってしまうところであった。 ・ ・ ・嫌な、予感がしたのだ。 否――― ・ ・ ・予感だけであったなら、どれだけ良かったか。 「いざとなれば、国に頼るまでですもの」 「――――――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 彼女は、笑みすら浮かべ。 「”魔女狩り”をご存知?」 「 ・ ・ ・、 ・ ・ ・ええ ・ ・ ・」 「私の夫は、魔法使いに殺されたのよ」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 ソフィーにとっては、余りにも残酷な言葉を残して去った。 「彼らに、哀れみなどありませんもの」 この街が――――――敵となった瞬間だった。 ソフィーはその場に崩れるように座り込む。 呼吸が、荒れ狂っている。 心臓が、どうにかなってしまいそうなほどにその鼓動を打ち鳴らしている。 ・ ・ ・あのひとの、想いは分かる。 そして、あのひとの、怒りも欠片ほどなら分かる。 だって、ソフィーも愛する夫が居るから。 その夫を、まさに、戦争に奪われそうになっているから。 まだ、ふたりに子供は居ないけれど ・ ・ ・そこに辿り付くまで成長は遂げていないけれど、きっといつか、存在する時が来ると想っているし、そう願っている。 そんなかけがえのない家族を得て ・ ・ ・もし、愛する夫を奪われてしまったら。 愛する我が子に食べるものすら与えられないほどに追い詰められたら。 自分とて、何をするか分からない。 そうはなりたくないけれど――きっと自分は、ハウルのためなら何でもする。 だから、あのひとを責めることなど出来はしない。 ・ ・ ・でも。 ・ ・ ・ ・ ・ ・だけど。 だからといって、割り切れはしない。 許すことなど、できるはずもない。 例え、あの婦人であったとしても。 どんな酷い境遇にあるひとだとしても。 ハウルを――――奪われたくない。 ・ ・ ・その為には。 振り切るしか、ない。 そして ・ ・ ・その為なら、喜んで自分はその答えを躊躇わずに選ぶだろう。 ソフィーは跪いたまま、祈るように指を胸の前で組み。 瞳を、閉ざして。 そっと、独りで泣き続けた。 涙が、枯れてしまうまで。 |
20060509
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
