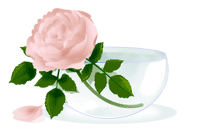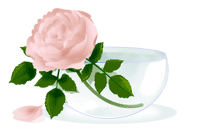空襲がぱたりと止んだのは、丁度二週間ほど経った頃だ。
ソフィーの店がある街までも、”婦人の外出禁止命令”なるものが施行された。
働き盛りの男性は皆、自国軍魔法使いの不足により一般歩兵として根こそぎ召集されてしまっているため、憲兵の役割までをも強いられている国の役員 ・ ・ ・つまり市長が直々に一件一件周り文書を配布している。
ソフィーもつい先日、それを受け取った。
その内容に頬を膨らませ思わず文句を紡いだ彼女を、ハウルは珍しく嗜めた。
そういえば港町の治安が乱れた際も、彼は再三ソフィーに”港町へ行かないように”とまるで父親のように彼にしては厳しく言い聞かせていた。
どうやら、彼女が思っている以上に ・ ・ ・状勢は芳しくないようだ。
いくらか冷静になったソフィーは、男手が不足している今、乱れた治安を取り締まる警察までもが存在していないのだから ・ ・ ・外出禁止は当然といえば当然の処置とも言えよう。国がそれを理解し、少しでも改善しようとさせている事を考えればまだこの国は正常だ――― ・ ・ ・そう思っていた。
・ ・ ・しかし。
この国は既に、後戻りのできない迷走を始めていたのだ。
今朝もまた、市長が扉を叩いた。
すっかり体調も良くなり、精神的にも大分安定したソフィーは完全に主婦業へと復帰していたので ・ ・ ・必然的に”公布文書”はソフィーが受け取ることとなった。
女性が外出禁止になったため、今は店も休業している。
けれども店の仕事が無くなろうとも、彼女の家庭における仕事は手に余るほどあるのだ。今朝も忙しなく家中を早足で行ったり来たりしていたソフィーはその文書を箒片手に目を通し―――
・ ・ ・絶句した。
瞬間、頭の中が真っ白になった。
悪い夢を見ている時と全く同じ感覚だ。
・ ・ ・これが夢であれば、どんなに良かったことか。
呼吸が荒くなる。
鼓動が重低音を刻むように体中に熱く響いている。
身体が、おかしなくらいに緊張していた。
けれどもすぐに我に返り、辺りを焦った風に見渡す。
ソフィーは窓際で本を読んでいる荒地の魔女を見つけ、思わず駆け寄る。
真昼の太陽の日差しを一身に受けている老婆を自らの身体で塞ぐように立つや否や、そのまま素早く振り返りカーテンを閉める。
部屋が、少しだけ薄暗くなる。
「おばあちゃん、窓際に居ては駄目。お部屋に戻りましょう」
自らの動揺はあと少しで極限に達する所だったが、そこは持ち前の自制心で抑えつける。声色も、高齢である荒地の魔女を下手に驚かせてしまわないように極力気を配った。
そうして平穏を装いながら、彼女自身も自らに対して、ひたすら”落ち着け、落ち着け”と、まるで何かの呪文のように何度も何度も心の底で諭しつづけた。
でなければ、全てが壊れてしまうと思ったからだ。
けれど魔女は、そんなソフィーの想いなど知るはずもなく、いつものように子供のような駄々をこねる。
「あたしはここがいいんだよ」
「おばあちゃん ・ ・ ・」
通常であれば、今のソフィーの精神状態を察すれば、この一言で頭に血が上ってしまうのが道理なのであるが ・ ・ ・彼女はそんな魔女の老婆に対しても、決して悪態など吐かないのだ。
いつかのように、自らの全てを開け広げ、偽り無き言葉と心で諭すのだ。
優しく抱きしめ、ありのままの思いを伝えるのだ。
・ ・ ・信じてもらわなければ、決して荒地の魔女は首を縦には振ってくれないと分かっているから。
それ以前にソフィーにとってその行為は、家族へ対する最低限度の礼儀だった。
「お願い ・ ・ ・」
抱きしめた老婆の身体は、思いの他いつかのような覇気も無く、柔らかく暖かだった。
今更ながら、荒地の魔女が高齢であることを痛感させられる。
少しだけ、寂しい匂い。 ・ ・ ・いつ終わりを告げる使者が訪れるか分からないほどの存在なのだと。
ソフィーは、抱きしめる腕に力を僅かに込めた。
「こんな理不尽な国の王様なんかに、おばあちゃんを取られたくないの」
「あらァ、王様があたしをご所望だなんて参っちゃうわねぇ」
悲痛とも言える切実なソフィーの言葉に、荒地の魔女は暢気にそんなことを言う。
けれども、頑なにその場へ留まろうとしていた意志はそこには既に無く、大人しくゆっくりと自室へ向かおうとしている所をみると――― ・ ・ ・どうやら、分かってくれたらしい。
ソフィーは、哀しげに微笑んだ。
少し前までは、ハウルと同等の洞察力を有していた荒地の魔女も ・ ・ ・こうして再建した城へ住まうようになりしばらく経った頃から、まるで子供のようになってしまった。
ふとした拍子にソフィーを手助けしてくれたり、助言してくれたりするのだが ・ ・ ・行動が、まるっきり幼子のようになってしまったのだ。 ・ ・ ・無理も無い。今の荒地の魔女はこの世界における平均寿命など、とうに越えてしまっているのだ。
その上、魔女現役の頃から異常なまでの魔力消費を重ねに重ね、禁呪にまでその手を染め、タブーとされていた生命の研究にまで没頭したが為に、サリマンによって危険とみなされ魔力を全て奪われ、本来の姿である老婆へと戻されてしまったのだ。
国中で流れているハウルの噂である”若く美しい女性の心臓を喰らう”というものは、そのまま荒地の魔女へと移行される。 ・ ・ ・それはデマでも噂でもなく ・ ・ ・”事実”なのだという。
以前、就寝前のベッドの中でハウルが言っていた言葉をふと思い出す。
”荒地の魔女に興味を持ったのは、僕と同じ噂を持っている魔法使いだったから。もしかしたら僕と同じ境遇のひとなのかもしれないと思って近づいたんだ。 ・ ・ ・だけどそれが”本当”だと知って、慌てて逃げ帰ったさ”
だから、「恐ろしい人だった」。
そう思い、ハウルは魔女から逃げ続けていたのだという。
その事実は、ハウルの心臓を手放そうとしなかった様を実際にその目で見たソフィー故、疑う余地も無かった。
だけれども、今の魔女は非力な老婆なのだ。
必ず誰かが傍にいて、支えてやらなければならない。
例えカルシファーに”お人よし”と言われようとも、家族となった以上、守ることは当然の義務なのだ。
・ ・ ・そういった考え方を、あまつさえ自らに呪いを掛けた魔女に対してするソフィーを、マルクルもカルシファーもハウルですらも、完全な形においては理解することができなかった。
けれども、”それがソフィーだから”という結論に至ってしまったため、今では誰も、何も言わない。ハウルにおいては、ソフィーが荒地の魔女ごと城へと飛び込んできた時点で彼女の意志をくんではいたのだけれども。
・ ・ ・荒地の魔女はつい最近まで、そんな哀しい立場だったのだ。
しかし、今ではカルシファーにとっては談笑の相手であり、マルクルにとっては祖母としての存在であったり、ハウルに至ってはもはや”ばあちゃん”扱いである。
荒地の魔女は、強力な力と優れた思考と引き換えに、家族というものを手にしたのだ。
それが彼女にとって、幸福なことであるのかどうかは分からないのだけども。
荒地の魔女を自室まで送り、リビングで魔法書を読んでいるマルクルに対しても、ソフィーはとりあえず自室に戻るようにと伝えた。
マルクルはハウルの影響なのか、ソフィーの様子を見て何かを察したようで、素直に頷いて焦ることもなくヒンを連れて分厚い魔法書を片手に二階の自室へと向かった。
・ ・ ・けれど ・ ・ ・一番心配なのは、ハウルのことだった。
彼は魔法使いのための国際的な会合に呼び出され、今は留守中だ。
鋭い彼であること、きっとこの命令書の内容とて薄々感づいてはいるような気もするのだが ・ ・ ・
―――もしかしたら、ハウルが呼び出された理由はこの命令書の事と関係があるのかもしれない。
ハウルが属している連合は、魔法使いが正しい道でその力を発揮できるよう ・ ・ ・つまり、貴重である魔法使いを圧政や弾圧から保護するために作られた、国際的な機関なのである。
いくら住んでいる場所がキングズベリーでも、ハウルが属している場所がその連合である以上、彼は”この国の魔法使い”という立場にはならない。あくまで中立的立場ということなのだ。
言ってしまえば、この城そのものが一つの小さな国なのだろう。
・ ・ ・ならば、心配は無いのだけれど ・ ・ ・。
そう、ソフィーが不安に駆られていた丁度その時。
扉の色が変わる乾いた金属音が彼女の耳を掠めた。
・ ・ ・ハウルが、帰ってきたのだ。
思わずソフィーは彼に掛けより抱きついてしまったが、彼はやはり察していたようで、それを受け止めてくれた。
・ ・ ・服も汚れていないし、傷を負っているようではない。
良かった、無事で ・ ・ ・と思った途端、ソフィーは全身から力が抜けていくのを感じた。
それに気づいた彼が、肩を抱き、背中を支えてくれる。
いつもの柑橘の香りが彼の美しい金髪から香り、それだけで安堵を覚えた。
ハウルは、まだ”あの命令”をその身に受けてはいない。
・ ・ ・だって、彼はキングスベリーの魔法使いではないのだ。
この城の、 ・ ・ ・この、小さな国の主なのだ。
だから、大丈夫。 ・ ・ ・大丈夫。
ソフィーは彼に抱きしめられながらも尚、そんな事ばかりを何度も何度も欠く事無く祈り続け、念じ続けた。
それなのに、不安と嫌な予感だけはどうしても拭えないのだ。
何故。 ・ ・ ・何故、何故、どうして。
・ ・ ・と。
落ち着いた、いつもよりもいくらか低い彼の声が降ってきた。
「市長が来たんだね。 ・ ・ ・受け取ったのかい?」
「 ・ ・ ・ええ」
「貸して」
「でも」
「いいから」
・ ・ ・どうやら今日の会合は、”これ”が問題ではなかったようだ。
只の定期的な集まりであったらしい。
故にハウルはこの事実をまだ知らなかったのだ。
それでも、感の鋭い彼はソフィーの様子から察してはいたようだ。
その正体は知らずとも ・ ・ ・市長が来たということと、また理不尽な法律か何かが制定されたのだろうと。
渋るソフィーに、ハウルは微笑を浮かべ、淡々と渡すようにと要求する。
その態度は事務的で、何の感情もそこには介入していないように思えた。
けれどそれが今は―――実に、頼もしく感じられる。
少なくとも、ソフィーは普通ではいられなかったから。
彼女がハウルへと渡したいくらか皺のできた公文書は ・ ・ ・物資不足のせいか実に質の悪い紙だった。これだけで今この国がどれだけ極限状態であるのかが知れる。
・ ・ ・そして、それを、見て。
ハウルは、僅かに瞳を細めた。
ソフィーはその様子を、不安げに見つめる。
居ても立ってもいられなくなり、思わず考えていることが口から出てしまった。
子供のようだと自覚はしていたが ・ ・ ・こんな命令、どう考えても普通ではない。
「 ・ ・ ・戦争で、最初に魔法使いを投入したのは ・ ・ ・この国なのよね?」
「 ・ ・ ・そうだよ」
それは以前、就寝前の語らいの中でハウルが教えてくれたことだ。
「その為に魔法学校が作られて ・ ・ ・沢山の魔法使いが死んだって」
「 ・ ・ ・」
「 ・ ・ ・なのに ・ ・ ・どうして ・ ・ ・?」
忍耐だけには自信があった。
今まで、何があっても欠片ほどの平常心くらいは維持できていたはずなのだ。
けれど、今回ばかりは。
・ ・ ・そんなソフィーをそのまま現すかのような、彼女の掠れた声に。
ハウルの、笑みが消えた。
「 ・ ・ ・ね ・ ・ ・、どうして ・ ・ ・?」
ソフィーは、この言葉しか紡げない。
「 ・ ・ ・どうして ・ ・ ・、 ・ ・ ・ねえ、ハウル、どうして?」
「 ・ ・ ・ソフィー」
「どうしてなの!?ねえ! ・ ・ ・教えてよ!わけが分からないわ!」
「 ・ ・ ・」
「どうして――― ・ ・ ・、どうして、”魔女狩り”なんか ・ ・ ・!!」
・ ・ ・こんな、ことを。
彼に叫んだとて、何も変わりはしないのに。
今は、自分がしっかりしなくてはならないのに。
一番辛いのは、ハウルなのに。
・ ・ ・それを分かって、いるはずなのに。
―――――”魔女狩り”。
それは、何も魔女そのものを示しているわけではない。
この場合、魔法使い全てがそれに当てはまる。
しかも、それは賞金制なのだ。
つまり、国民が王宮へ魔法使いの居場所を知らせれば、その国民は大金を得ることができるのだ。 ・ ・ ・物資も、金銭的にも絶望にさらされているこの国の民にとっては、絶好の機会とも言えるのだ。
そして、国の政治に対する異端者をも”魔法使いだ”とでっち上げれば、魔女狩りという名のもとに”政治”と称してその者を処刑することだってできる。
そして、連行されてしまったら最後、理不尽な裁判にかけられ名誉を傷つけられた挙句、理不尽な死刑判決を受けるのだ。
かつてのキングズベリーでもあったことらしい。
先の戦争がそうだった。
魔女狩りと称し魔法使いをかき集め、あの”自己犠牲呪文”を敵国へと使わせたのだ。 ・ ・ ・サリマンの恋人である”アルストロメリア”がまさしくその魔法使いだった。
・ ・ ・下手を、すれば。
下手に外へ出れば。
ハウルが、理不尽な理由で王宮へと連行されてしまうかもしれない。
そんな、酷いことが。
何故、出来る人間がいるのだろう。
どうにもできない感情。
迸る怒り。
湧き上がる熱い感情。
全てを、全身に感じたまま。
・ ・ ・ハウルが帰ってきて、顔を見た途端。
・ ・ ・今までソフィーが押さえつけていた全ての冷静というものが、怒りという熱に掻き消されてしまった。荒地の魔女や、マルクルの前ではできていた平穏な装いが ・ ・ ・何故、よりによって ・ ・ ・一番守りたい、守るべき存在である彼の前では出来ないのだろう。
・ ・ ・出来なく、なってしまったのだろう。
心の中では冷たい自分の考えが他人事のようにめぐりにめぐっている。
けれど、口から放たれる言葉は悲鳴のような言葉ばかり。
ぼろぼろと、涙ばかりが零れ落ちる。
泣いている、場合などではないというのに。
そんな彼女を、ハウルは只そっと宥める。
髪を撫で、頬に触れ、額に口付ける。
その仕草は、生前のソフィーの父そのものだ。
・ ・ ・それに、何かのまじないを上乗せしていたのだろうか。
発作のような怒りが、次第に ・ ・・消えはしないものの、落ち着いていく。
―――恐らく、鎮静剤のような術なのだろう。
その上で、ハウルは囁くように言った。
・ ・ ・ソフィーの耳元へ唇を寄せ、確実に、届くように。
「大丈夫 ・ ・ ・僕は”連合の”魔法使いだ。立場を考えれば王宮は僕を連行することも逮捕することもできない。この命令書には国内の魔法使いと限定されてる」
「もう王様は立場なんかを考られるような人ではなくなってしまっているわ!こんな命令、正常なんかじゃない!」
「ソフィー」
ハウルが、そっとソフィーの頬に唇を寄せる。
「大丈夫。 ・ ・ ・そうだとしても、僕を逮捕できるような兵士は王宮には存在しない。例え王様の命令でも、実行するための動力がなければそんな物は只の紙切れだ」
「 ・ ・ ・だけ、ど ・ ・ ・」
頭では理解している。
ハウルの言っていることも分かる。
常識的に考えれば、ハウルや自分達に王宮が手出しできるわけがないのだ。
自分たちに手を出したその瞬間に、キングズベリーは世界の敵になるのだから。
戦う意志の無い中立国相手に一方的な圧政を強いることは、それすなわち、立派な国際法違反なのだから。
・ ・ ・だけど。
果たして、今のこの国に、それを理解するほどの思考が存在するのか。
こんな異常な命令書などを出す、この国が。
震えるソフィーに、ハウルは実に静かな声色で囁いた。
・ ・ ・信じられないほどに落ち着いた声だった。
「 ・ ・ ・幸い、連合もキングズベリーの動きを読んでいた。治安状態は最悪だし、何より先の戦争と同じ末路を辿ることになるんじゃないかって懸念すらしていたさ」
「先の戦争・・・、 ・ ・ ・それって ・ ・ ・、魔法使い達の、自爆のこと!?」
「連合は黙っちゃいないだろうね。この情報も、今頃連合には筒抜けってわけさ」
それは、果たして安堵しても許されるような状況だといえるのだろうか。
そうなれば、今度はその連合がこの戦争に介入することになってしまうのではないのだろうか。そうなってしまえば、ハウルは――――――――
湧き上がり、止まることを知らない不安は次から次へとソフィーを煽る。
けれど、必死に何度も言い聞かせた。
とにかく落ち着かなければ。
・ ・ ・この城において、”魔法使い”に属さない存在は自分だけなのだから。
婦人の外出禁止は施行されてしまってはいるが、今回のこの”命令”からこの城の魔法使い達を守れるのは自分だけなのだから。
・ ・ ・何があっても。
ハウルが、マルクルへ今後のことを伝えるために二階へ向っている、その間。
ソフィーは深く、深く――何度も深呼吸をした。
身体の中に、心の中に、ずっと潜んでいる怯えの種すらも吐き出してしまうように。弱音を吐いてしまわぬように、精神を新鮮な空気で清めてしまおうと思った。
・ ・ ・大丈夫。
大、丈夫―――――
怖くなんか、ない。
この国も。
王様も、兵士も、戦争も。
マルクルの無邪気な笑顔も。
ヒンの慣れ親しんだ鳴き声も。
おばあちゃんの穏やかな微笑みも。
カルシファーのやんちゃなお話も。
ハウルの、全ても。
渡しは、しない。
例え――――それが、神様なのだとしても。
この時。
そんなソフィーの悲痛な願いと、その覚悟を。
ハウルすら、察することができずにいた。
もし、今ここで彼が”ぎざみみハーゼ”を再び読めば。
・ ・ ・悟ることが、できていたかもしれない。
今の、うちに。
手遅れに、ならないうちに。