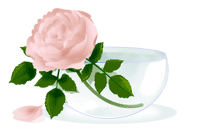
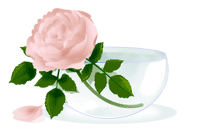
8
|
繋いだ手は、こちらの方が少しだけ暖かかったようだ。
ハウルの体温は、少しだけ低いように思える。 そんな事を感じながら、変わらぬ調子で街を歩き ・ ・ ・入った喫茶店においても周囲だけはあれやこれやと勝手にハウルを見てはひそひそと何かを話し出す。 ソフィーに気を遣ったのか、一番端の ・ ・ ・調度大きめの観葉植物の影になる二人がけの席を彼は選んだ。 ソフィーが落ち着いているので、ハウルもこれといって何も言わない。 これで彼女が泣こうものなら、何かをするのだろうけれども。 それも、彼のことだから、強かに、相手が気がつかないところで。 ・ ・ ・それが何かは、具体的には想像できなかったけれども。 けれども野次馬というのはご苦労なことで、こちらから視界から離れたというのに、あちらの方から堂々と忙しなく席を移動してくるのだ。 ・ ・ ・ハウルの方からはその様子が見れるようだが、ソフィーにとっては背後で起こっている出来事なので振り向かなければその光景は見ることができない。 なので思わず気になって振り向いてしまったが。 ・ ・ ・失敗だった。 瞬時に向き直る。 恐ろしい ・ ・ ・、恐ろしすぎる。 この喫茶店は女性客に評判の店だ。 故にソフィーもこの店を好んで入ったのだが ・ ・ ・。 見れば裕福な貴婦人ばかりではないか。 学生とは思えない立派なドレスに身を包んだ少女達もいた。 ・ ・ ・というか何故こんな時間帯に少女達がいるのだろう。 今日は平日なのに ・ ・ ・学校に行かなくてもいいのだろうか。 ・ ・ ・ああ、この期に及んで説教なんてしている場合ではない。 とにもかくにもそんな傍目からみれば美しい女性達が、まるでハウルのことを非売品の宝石を見つめるような憧憬の眼差しで、しかも群がってみているのだ。 それこそ、恥も外聞もなく。 ハウルが昨夜、”飴にたかる蟻のよう”と称していたが正にその通りだった。 彼があそこまで疲労困憊に陥ってしまった理由を今更ながらに痛感する。 気にしない、とは思っていたものの ・ ・ ・ここまでされればさすがに怖い。 ・・・というよりもハウルの方が怖がっているのではないのか。 確か以前、こういった女性達を”嫌いだ”のようなことを言っていた。 好ましく思っているはずがない。 ・ ・ ・というか好ましく思えるようであればそれはそれで心配だが。 この場で”大丈夫?”、等と尋ねるのも何だかおかしな気がするし、何より背後の集団に聞かれてしまう。 ・ ・ ・その後のことを想定すると ・ ・ ・。 ・ ・ ・いや、考えるのはよそう。 とにかく平常心でいなければ ・ ・ ・、と。 そっと、ハウルの顔を盗み見るが。 彼は、思いのほか――――平然としていて。 微笑すら浮かべてソフィーへと話しかけてくる。 「ソフィー、この店の常連だね?」 「へっ?」 「分かるさ。だって迷わずこの店を選んだじゃないか」 「あっ、ああ、 ・ ・ ・ええ、そうね ・ ・ ・よく一人で来てたから」 普通に、会話をしてくる。 背後の集団など視界に入っていないようだ。 いや ・ ・ ・ハウルにとっては目の前の光景 ・ ・ ・というか、惨事というか ・ ・ ・。 とにかく、余り見せたくはない有様だ。 ソフィーも背中で感じ取ってはいるが ・ ・ ・同様に、想像もしたくない。 「へぇ ・ ・ ・、一人で?」 「そうよ。 ・ ・ ・私だって帽子を作ってるだけじゃなかったの。たまにはこっそり美味しいものだって食べにいきたいって思ったわ」 そんなハウルに背中を押される形で、ソフィーもだんだんと背後の世界のことなど気にならなくなっていった。 ・ ・ ・いや、気にしてなるものかと自らに言い聞かせた。 あそこは別世界だ。 違う世界なのだ。 ・ ・ ・あながち間違ってはいない。 それにしても、あれだけ美人なら、相手選びは苦労をすることもないだろうに。 裕福なようだし、生活に困っているようでもない。 それなのに何故、あんな行動を起こせるのだろうか。 ふとソフィーは不思議に思ったが ・ ・ ・ それだけハウルが凄まじい存在感を有していることの表れなのか。 それとも、男性も、美人であればよい ・ ・ ・などとは思ってはいないのか。 思いつく答えは、ソフィーではそれが精一杯だった。 そんな彼女の脳裏で繰り広げられている、言ってしまえばどうでもよい予測の向こう側で、ハウルは全く違う会話を淡々と、囁くように進めている。 そして何故か ・ ・ ・どこか、探るような眼差しで。 「なら、二人で来たのは初めて?」 「そうよ。 ・ ・ ・私、あまり出かける方じゃなかったから ・ ・ ・」 ハウルが連れ出してくれなければ、ソフィーは自分のために散歩すらしない。 以前は、この戦時中に、街では兵が群がっているというのに、そんな場所へと自ら赴くなんて怖くてできない ・ ・ ・というのが本音であったのだが。 今はきっと、家の居心地が余りにも良くて、出かける心境にならないからだろう。 ・ ・ ・と。 ウェイトレスが遠慮がちに二人分の冷水を運んできたことによって、ソフィーはようやく我に返った。 ・ ・ ・そうだ、ここは飲食店。 早急にメニューを決めなければ、只のはた迷惑な客に成り下がってしまう。 ソフィーは大体頭の中で既に決定しているようなものだったので、メニューをハウルへと手渡した。 ・ ・ ・目前に差し出されたので、彼もそれを普通に受け取るが。 「ソフィーは決めたの?」 「”常連さん”だもの」 「ああ、そうか。 ・ ・ ・どうしようかな。よく分からないんだよね ・ ・ ・僕」 言いながら、視線をメニュー上へと流す。 ・ ・ ・ソフィーは”おや?” ・ ・ ・と思いながら ・ ・ ・ 「 ・ ・ ・ハウル、もしかして ・ ・ ・」 「ん?」 「こういうお店って、あまり来たことないの?」 今更ながら、そんな単純なことに気付いたのだ。 どうして気付かなかったのだろう。 ・ ・ ・というよりも、彼自身のソフィーをエスコートしてくれる際の仕草や表情が、それはもう手馴れていて ・ ・ ・彼女もまた、”場慣れしている”と思いこんでいたのだ。 けれど、それは大きな間違いだったのだ。 第一、彼が場慣れなんぞをしているはずがない。 ・ ・ ・何故か? 答えは簡単。 ハウルは子供の頃からソフィーだけを探し続けてきたのだから、過去にこういった場所へと連れ出すような存在も居ないし、 ・ ・ ・第一、男性が一人でくるような場所でもない。 ・ ・ ・結果、彼が場慣れなどしているわけがないのだ。 ・ ・ ・そういえば以前二人で似たような店に入った際も、ハウルはメニューを自ら決めず、ソフィーに託していた。 ソフィーは自らの気遣いの無さを痛感する。 ”来たことないの?” ・ ・ ・だなんて、なんとも無粋な質問ではないか。 そう、後悔したのだが ・ ・ ・ 彼はただ―――そっと笑って。 「ソフィーはどれ?」 「えっ? ・ ・ ・えーと ・ ・ ・、これ。一般的なんだけど ・ ・ ・子供の頃から大好きなの」 ・ ・ ・と、指差したのは栗のケーキ。 彼女の家においては、亡き実母の思い出の味だった。 ソフィーがこの店を好んでいるのは、味が母のそれと似ているから。 「そういえば私、ハウルが甘いもの食べてるところって見たことないわ」 「ちゃんとした食事自体、君が来てからだよ。まともに取るようになったのはね」 「そうなの? ・ ・ ・それまで、どうしてたの ・ ・ ・?」 ハウルはメニューのページを繰りながら、声を潜めて言った。 ・ ・ ・ソフィーだけにしか聞こえない声色だ。 「栄養剤。 ・ ・ ・あとは水くらいかな」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・」 「物心が付いたときには、そうだったよ」 ・ ・ ・まあ、物心が付いたときには、気が付いたら心そのものも無かったけど。 ・ ・ ・そんな悲しいことを、彼は淡々とソフィーへと語り続けた。 まるで過去の思い出話をつらつらと述べるように。 ソフィーは言葉が見つからず、ただ彼の、今は少しだけ細められて下を向いている地球色の双眸をそっと見つめる。 「何を食べても、味がしないからね。 ・ ・ ・たまにマルクルには悪いと思って食事の用意はしたけど ・ ・ ・、やっぱり、味が無いと気持ち悪くてね」 「 ・ ・ ・そう」 ”ハウルさん、絶対食べないと思うよ。” ・ ・ ・マルクルの言葉が突如としてソフィーの脳裏に蘇る。 彼は全てを知っていて、あの言葉を紡いだのだろうか。 ・ ・ ・何故あの時、自分は何も気付かなかったのか ・ ・ ・とは思ったが。 知るわけが、ないのだ。 その手段もない。 それは仕方のないことだった。 ・ ・ ・ソフィーはそう思い直した。 それに今、彼は無理をしてこの場にいるわけではないのだから。 ・ ・ ・これから一番大事にしなければならないのは、今なのだ。 その次に、未来。 ・ ・ ・そして ・ ・ ・尊重しなければならないのは、過去。 過去があるから、今の道筋を定めることができるのだ。 過去は、そのヒント。 故にそれに囚われてはならない。 ・ ・ ・忘れても、ならないけれど。 「 ・ ・ ・今は、大丈夫?」 「今? ・ ・ ・うん。今は平気。心が戻った途端、急に空腹になってね。最初は味を感じるのが精一杯で、どれが美味しいのかも分からなかったけど ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・」 「今はね。 ・ ・ ・あれが食べたいな、とか ・ ・ ・思えるようになったよ」 そう、囁いた途端。 ハウルはテーブル越しに、ソフィーの手に自らの手をそっと重ねてきた。 突然生じた温もりに、思わずソフィーが驚いていると。 「気付いてたよ。ソフィーは、いつも真剣に僕のことを考えてくれてるって。 ・ ・ ・君も、本当は気付いてたんじゃない? ・ ・ ・僕のこと」 「―――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 そっと、重ねられているだけのはずなのに。 ・ ・ ・なんて、強い力。 そう感じるほどの何かが、彼の美しく細い指先には存在していた。 それは、意志なのか。 思いなのか ・ ・ ・判断はしかねたけれど。 第一、ソフィーは今この時、それどころではない。 星の瞳に捕まえられて、逃げ場が無い。 苦しい―――、とても、苦しい。 けれど、それは ・ ・ ・とても心地の良い苦しみ。 恋愛に関する心理状態というものは、常に何かが矛盾しているものなのか。 「ちゃんと、分かってる。 ・ ・ ・いつもソフィーが港町に行っている理由も」 「 ・ ・ ・えっ?」 「あの、オレンジの紅茶。僕が美味しいって言ったからだろう?」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・あっ ・ ・ ・、えっと、それは」 どうして言い訳みたいな言葉ばかりが頭に浮かんでくるのだろう。 ・ ・ ・彼がそこまで自分のことを見ているとは夢にも思わなかったためか。 ハウルは常に淡々としていて、やることなすことスマートで ・ ・ ・、故にそこまで見抜かれているとは、ソフィーは考えもしなかった。 彼女なりに、必死だったのだ。 心を取り戻すまで、彼が何かを食したところをみたことがなかったから。 お茶を飲んでいたのは最初のあの朝食の場面で確認したので、とりあえずそこから攻めて行こうと ・ ・ ・様々なブレンドを研究した。 ・ ・ ・もともとソフィーは、凝り性なところがあるのだけれど。 「ま、マルクルは好き嫌いがハッキリしてるけど ・ ・ ・、あなた何も言わなかったから」 「うん」 「どれが好きなのかしらって思ったら ・ ・ ・思いついたのは、紅茶で ・ ・ ・」 「何故?」 「 ・ ・ ・あの頃は、あなたが何か食べてるところって見たことなかったから ・ ・ ・。お城に初めて来て、あなたが朝ご飯を作ってくれて ・ ・ ・その時に飲んでいた、お茶くらいしか」 それも、一口だけだったけれど。 「それに、あなた ・ ・ ・柑橘系好きでしょう ・ ・ ・?」 「うん。 ・ ・ ・どうして分かったの?」 「 ・ ・ ・あ、あなたの匂いだもの」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・」 あの頃は正直あてずっぽな状態であったが ・ ・ ・今は毎晩一つのベッドで共に眠っているのだからそれは確信となっている。 そんなソフィーの指摘に、ハウルは少しだけ驚いたようだ。 瞳が、一瞬だけだけれども見開かれたから。 「味が分からない、なんてことは気付かなかったわ。でも ・ ・ ・食べることがあまり好きじゃないのかなって ・ ・ ・勘違いをしていただけ」 「うん」 「だから ・ ・ ・少しでも、好きになってもらえれば ・ ・ ・って ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・うん」 その、少しだけ驚きに染まっていた美貌が ・ ・ ・優しい、笑みに変わって。 重ねていたソフィーの手をそっと取り、その甲に ・ ・ ・唇を寄せる。 そして―――優しい声。 穏やかでありながら、核は常に光で溢れている地球色の双眸が捕らえて。 「 ・ ・ ・ありがとう ・ ・ ・」 お礼を、ひとつ。 ・ ・ ・もう、ソフィーは正直、どうにかなってしまいそうになった。 まさかこの場でこんなことまで暴かれて、こんな形でお礼をされるだなんて。 彼がここまで、自分のことを見ていてくれただなんて。 そんな、半ば放心状態のソフィーに。 水を持ってきて、そのままメニューを聞こうと突っ立っていたウェイトレスの遠慮がちな声が降り注ぐ。 ・ ・ ・それは霧雨ほどの弱々しさだったが ・ ・ ・ ソフィーにとっては、竜巻だった。 顔をこれ以上はないというくらいに真っ赤に染め上げたソフィーを見て ・ ・ ・当事者の一人でもあるハウルは、思わず笑った。 確かに恥をかいたようなものなのだけれども ・ ・ ・それはそれで、穏やかなときが流れ、恐ろしいと感じる唯一のものは野次馬の貴婦人達だけ。 なんて贅沢な街なのだろう。 決して、平和な国とは呼べぬのに。 そんな世の中の流れに逆らうように、この町は穏やかだった。 優しくそよ風のようにさらさらと流れ、それはとても幸せな空間にすら感じられた。 ――――けれども ・ ・ ・―――― この、混乱した国において ・ ・ ・そんな幸せは長続きしないであろうことも。 ソフィーは―――心のどこかで覚悟していた。 そして、それは。 翌日の朝、その通りになった。 |
20050909
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
