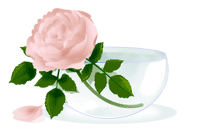
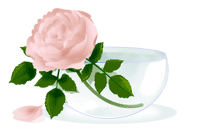
5
|
あの真昼の出来事からハウルが帰宅するまでの間、ソフィーは決して冷静であったわけではない。ああして彼の部屋で彼の帰りを待つという形に落ち着くまでにはさまざまな経緯があったのだ。
自己嫌悪の奈落に自ら落ちていきそうになったソフィーは、自己防衛本能が働いたのか、とにかく体調が悪いということすらも忘れて家事に専念し、これといって行事もないのに夕食に力をいれてみたりと、とにかく”自分が自分らしく居られる状況”へと持っていこうと躍起になっていたのだ。 ・ ・ ・まあ、おかげで部屋はこの通りとても綺麗になったし、気になっていたキッチンの換気扇の掃除もようやくできた。 この日ハウルは夕食には参加できなかったものの、いつも以上に手のこんだ夕食はマルクルと荒地の魔女に絶賛された。 やはり食べてもらえること、喜んでもらえることは何より嬉しい。 たまにはああいう混乱状況になるのも良い気分転換だろう、などといささか無理のある解釈で、無理やり自身を納得させ、通常であれ通常であれと必死だった。 けれど、夕餉を済ませ、後片付けも全て終えた後 ・ ・ ・やはり心の底で何かが沸騰するように形容のし難い苦しみに襲われたのだ。 昼間のように落ち着かない仕草までは出さなかったものの ・ ・ ・結局ソフィーはハウルの帰りを待つ間にしようと思っていた読書も手につかず、外の空気を吸いがてら花園へと赴いたのだ。 その夜、月こそ顔は出さなかったが――その分星はいっそう輝きを増し、煌々と輝いていた。気ままに花々の間を縫うようにゆっくりと歩き続け、途中父の墓前でその足を休めた。 ハウルと、城の住人達が父をこの場所へと連れてきてくれたのだ。 あそこは暗く冷たいだろうと。 ひとりぼっちで寂しいだろうと。 ハウルはまるで生きた人間を招くように父の墓をこの花園へと”引越し”した。 それが、どんなに嬉しかったことか。 墓と言えど、ソフィーにとっては父は父のままである。 返答が無いとは承知の上で、正直にありのまま白状する。 ・ ・ ・普通、父親にするような相談事ではないような気もするが ・ ・ ・ なに、問題などなに一つありはしない。 きっと父は今すぐ目の前で、自分には聞こえない声と言葉で色々とお説教をしてくれるに違いない。 「ねえ、お父さん。夜遅くにごめんね。 ・ ・ ・これも夜遊びっていうのかしら」 だったらこれがはじめての夜遊びね、とソフィーは笑ってみせる。 ・ ・ ・笑えるようになったのだ。 こうして、父の墓をありのまま受け止めながら笑える日がやっときたのだ。 「 ・ ・ ・今日はハウル、夜遅くまでお仕事なの。 ・ ・ ・だけど私 ・ ・ ・あれくらい ・ ・ ・で、勝手に怯えて閉じこもっちゃって ・ ・ ・ハウルに”いってらっしゃい”って ・ ・ ・言ってあげられなかったの。 ・ ・ ・奥さん失格ね」 けれどソフィーにとっては”あれくらい”などでは到底すまないことだったのだ。 世間一般では”おかしい”といわれてしまうのだろう。 わかってはいても ・ ・ ・仕方が無いのだ。 事実に嘘など吐けはしない。 けれどソフィーから見ても、今の自分とハウルとの関係は”恋人”の枠のまま抜け出せずにいるような気がするのだ。 手を繋ぐだけでかなりの勇気がいるし、抱きしめられれば頭の中が真っ白になってしまうし、キスなど慣れたものではない。 ましてや昼間のような行為にまで及べば ・ ・ ・そこから何時間かは放心状態に陥ってしまい、当分自分の思考は使い物にならないものへと変じてしまうのだ。 これではまるで ・ ・ ・恋人としてもまだまだ未熟ではないか。 ハウルではない。 ・ ・ ・あくまで、自分だけが取り残されているような気がするのだ。 そう想うと、不安で不安でたまらなくなる。 ハウルがこんな自分のことをどう思っているのかが気になって仕方が無い。 その一方で――― ・ ・ ・怖くて怖くて堪らない。 「 ・ ・ ・ねえ、お父さん。 ・ ・ ・夫婦って ・ ・ ・、どういうものなの?」 その恐怖を、思わず墓前でまで呟いてしまう自分は ・ ・ ・親不孝ものだ。 拝みもせずに愚痴ばかりを通すだなんて。 「私はちゃんと、ハウルの奥さんになれているのかしら」 ・ ・ ・正直にいってしまえば ・ ・ ・未だに結婚したという自覚がないのだ。 自ら望んで式を挙げなかったからだろうか。 ハウルはハウルで式のことなど”もう結婚しちゃってるのと同じだからね”などと軽く笑ったものだったので、大して気にも止めなかったようだが。 「私の、ハウルのことが大好きって気持ち ・ ・ ・ちゃんと伝わっているのかしら」 ・ ・ ・などと。 思ってはいても、決して口からは出はしない言葉がぽろぽろと零れ落ちていく。 それはもう、不思議なまでに。 「 ・ ・ ・ちゃんと伝えるためには ・ ・ ・ああいうこと、しなきゃ伝わらないのかしら」 ・ ・ ・と。 言った途端に、それまで影を潜めていた北風が思い切り吹き抜けていくので驚く。 それまで気配すら感じなかったのに、突然。 ・ ・ ・偶然、なのだろうか。 気のせい、なのだろうか。 言葉が、聞こえたような気がしたのだ。 ―――ソフィーだって、口で言ってくれなきゃ分からないってよく怒っていたよ。 「 ・ ・ ・あ」 ざわざわと、草花が揺れる音が響く。 雲が早い速度で流されたとき、今日は出ていないとすっかり思い込んでいた満月が突如その姿を現し―――ソフィーは心奪われる。 目が ・ ・ ・覚めたような気がした。 ぼうや、わたしのかわいいぎざみみぼうや。 お外はとっても危険なの。 おそろしい蛇や狼が、いつでもおまえを狙っているからね。 ぼうや、わたしのかわいいぼうや。 わたしはすこしおまえの元を離れるけれど じっと、ここで息を潜めているんだよ。 野ばらがおまえを守ってくれるからね。 決して外に出てはいけないよ。 おまえは頭がいいけれど、とても小さくて力の弱い子なのだから。 わたしがいなければ、おまえは生きていけないのだから。 おまえがいなければ、わたしは生きていけないのだから。 「だけどハーゼは外に出た」 耳に触れている彼の胸から、低い声が振動と共に伝わってくる。 まどろみの中の静かな語り。 過去の断片を一つずつ拾っていくような ・ ・ ・砂浜で小さな貝殻を探りあてるような、ゆっくり、ゆっくりとした調子でハウルの語りは続く。 「かあさんハーゼのいいつけを守らなかったのさ」 湯浴み後の、すべらかな指先が銀糸を梳いていく。 心地よく、ソフィーのまどろみは進んでいくばかり。 「ハーゼは過信していたんだ。かあさんハーゼがいなくたって自分は生きていけるってね。 ・ ・ ・無理だって分かっているくせに」 深夜の、ハウルの寝室。 あれからソフィーは何の躊躇いも無く、彼とベッドを共にした。 入浴を済ませた彼は”今日は疲れたし面倒だったから”と、染めたままの美しい金髪を指差し苦笑いを見せた。 それからソフィーも身支度を済ませ、彼女自身驚くほどに緊張もせず再び彼の寝室へと入ることができたのだ。 ベッドに入ると、自然な流れで軽いキスを2、3度ほど交わし ・ ・ ・ そして、今に至る。 ハウルの語りが、心地よく続いている。 「そしてハーゼは外に出て ・ ・ ・恐ろしい蛇に噛み付かれた。だけど駆けつけた母さんハーゼが命がけでハーゼを助けた。ハーゼは命拾いしたけれど ・ ・ ・その耳は噛み切られ、ハーゼは”ぎざみみ”になってしまったのさ。 ・ ・ ・大好きな母さんハーゼが死ぬことすら厭わずに浅はかな自分を救ってくれた ・ ・ ・その忌まわしい傷跡は、ハーゼの心を愛する者へと向けさせたんだ」 「 ・ ・ ・それで ・ ・ ・守られる立場から、守る立場へと変わっていくのね」 「そう。 ・ ・ ・ハーゼは自分のためじゃなく、母さんを守るために様々な知恵と生きる手段を覚えていく。自分のためだけのときはできなかったことが ・ ・ ・母さんを守るためなら、不思議なことになんだってできたのさ」 初めての夜の時よりも、遥かに甘い時間だとソフィーは感じた。 昨夜よりもハウルが、明らかに大人で、酷く落ち着いているせいだとも思う。 仕事をしてきたということもあるのだろうか ・ ・ ・それとも他に何か理由があるのだろうか。不思議なことにソフィーは、まだ”片想い”だった頃の心境に近づきつつあった。 それは決して心が離れてしまったということではない。 正式に同居することとなってから目まぐるしいほどの時を過ごし、落ち着いた頃には全てを超越してしまい今では夫婦だ。 ゆっくり恋を感じている時間など無いに等しかった。 そして勿論、決して結婚したことを後悔しているわけではない。 結婚も、夫婦の形もひとそれぞれだが、通常であれば”恋愛を経て”婚姻を結ぶものなのであろうが―――自分たちは、どうであろう。 まるで”恋愛をするために”結婚したような気すらする。 事実、下世話な話になってしまうが、ハウルとソフィーは結婚するまで一度も身体を重ねることなく、過ごした時間も決して長いとは言えない。 双方とも、それ以前に異性と通じたことすらない。 ソフィーの方はそこまでの恋愛に発展しなかっただけで、恋愛そのものの経験も、友人以上の異性の存在も無かったとは言えないが ・ ・ ・ハウルは別格だ。 子供の頃に時を旅するソフィーと遭遇し、それからずっと彼女だけを探し続けてきた。両親に手放され、唯一の肉親である叔父を目の前で失い、力を欲し、心をも失ったハウルが――もし、あの場でソフィーと出会わなければ―――まず間違いなく、彼は道を踏み誤っていただろう。 ハウルは恋愛を超越し、存在としてのソフィーを求め続けてきた。 ・ ・ ・故に、”恋愛”としての自覚はソフィーと出逢う前にゆっくりと為されてきたものなのだろう。 つまりハウルはあの星の降る夜、ソフィーに一目惚れをしたのだ。 愛に理屈は無いというが――出逢ってから見つけ出し再会を果たすまでの間、ハウルはずっとソフィーへの想いを胸の中で暖め続けてきたのだ。 故に、ソフィーが自分以外の他の誰かと結ばれることなど、到底考えもしなかったのだろう。心の成長が止まってしまった彼の浅はかさが、会えない間の彼自身を皮肉にも支えていたのだ。 けれど ・ ・ ・”結婚”をして、一つだけ変わったことがある。 それはハウルのソフィーに対する姿勢だ。 基本的にはあまり変わりはないのだが ・ ・ ・ 気ままで自分勝手な性格は今ではすっかり見る陰もなく、別人か、とすら思えるほどに彼は変わった。少し外出するときでも、どこの街のどの店にいるかを告げた後、しっかりと彼女に”いってきます”と言い残してから家を出る。 これではまるで幼い子供をよくできました、と褒めているようにすら感じられるであろうが ・ ・ ・これはソフィーにとっては大きな変化なのだ。 ハウルがそういう習慣を身に着けたことで、彼女の方もそれに従わなければならなくなったのだから。 ・ ・ ・まあ、彼のことだから無理強いなどしないのだけれども。 そしてそれとは別に、昼間のような行為もそうだ。 彼は衝動的に、ソフィーの唇に触れたがる。 場所をも問わずに触れたがっているのが鈍感なソフィーにすら分かってしまう。 ・ ・ ・何故か。 答えは簡単だ。 それはハウルが、”キス以上の愛情表現”を知らないからだ。 彼自身、そういった知識に乏しいことを自覚しているために一種のコンプレックスのようなものとなっているのだろう。時折不安げにソフィーを見る。 その”不安げ”な表情も、傍目からみれば麗しく美しい無表情と捉えられてしまうのだろう。ソフィー故に表情のわずかな変化すらも見分けることもできるのだ。 そういうときは、なるべくハウルに触れるようにしている。 手を握ったり、ただ近くに寄り添っていたり、 ・ ・ ・時には勇気を出してキスだってする。自分でも甘いということは痛いほどに自覚しているのだが ・ ・ ・ あんな表情で毎日見られてもみてほしい。 色々な意味で耐えられない。 けれども、そんなハウルを”愛しい”と思う自分がいるのも真実だ。 そして、それを補うほどの知識がない自分を、うらめしいとすら ・ ・ ・思う。 まあ、逆にあればあったで彼を傷つけることになるような気もするのだが。 そんなソフィーの複雑な心境など知らず、ハウルはそっと囁くように語る。 話題は物語から、別のものへと変化していた。 「ハーゼは母さんのいいつけを破って外に出た。だから”ぎざみみ”になってしまった。僕はソフィーの言うことをきかないで戦場に行った。 ・ ・ ・だから怪物に化した」 「 ・ ・ ・、 ・ ・ ・え?」 「母さんハーゼは命がけでハーゼを守った。ソフィーは命がけで僕を助けてくれた。 ・ ・ ・愚かな僕らの判断ミスで、愛する人は傷ついた」 そっと、繊細な指が頬に掛かる星色の髪を耳にかけるように梳き、ハウルはソフィーの瞳を真っ直ぐと射抜くようにじっと見つめ、そっと言う。 ・ ・ ・予想外の言葉を。 「 ・ ・ ・ごめん」 「 ・ ・ ・えっ?」 「僕はあの時 ・ ・ ・君を、母さんハーゼにするところだった」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・」 「そして僕は ・ ・ ・ハーゼそのものさ」 その言葉の意図を読めず、ソフィーはただ小首を傾げて眉を寄せた。 確かにハーゼの浅はかさが母さんハーゼを追い詰める結果となってしまったのだが ・ ・ ・その後ハーゼは成長し、母さんハーゼを立派に守っていた。 寧ろ、母さんハーゼは幸せだったはずなのに。 ・ ・ ・何故? 自分だってそうだ。 ハウルは確かに不安定で気侭であったし、ソフィーもそれなりに振り回されたものだが ・ ・ ・彼は懸命に空襲から自分たちを守ろうと戦ってくれた、抗ってくれた。 その想いを感じたとき、明らかに自分は幸せだと思っていたのに。 その疑問は、意外な形で解明された。 多大な驚愕と戸惑いと衝撃とともに、明かされたのだ。 ――――― ・ ・ ・突然。 ハウルの強い腕が彼女の背中を引き寄せたかと思うと、何かを考える暇など一切与えぬままに ・ ・ ・昼間と同じ、キスをしてきたのだ。 「 ・ ・ ・ ・ ・っ ・ ・ ・ ・ ・ ・!」 拒絶とか、嫌だとかそういう意味ではなく、ただただ驚愕と衝撃でソフィーは無意識のうちに身を強張らせた。 何の前触れもなく、それこそ僅かな予感すら無いまま彼からこんな直接的行為をされたのは ・ ・ ・覚えている限り、初めてのことだ。 頭の中は真っ白だ。 ただ、彼から与えられる熱い感触だけが強く彼女を支配する。 思考という思考を根こそぎ抉られていくような感覚だ。 理屈すらも屈託の無い彼からの圧力にいとも容易く破壊されてしまう。 後には ・ ・ ・彼への愛だけが如実に残る。 全ての殻をはがされて、行き場の無い心臓が晒されているような ・ ・ ・ 実に不思議な、この感じ。 唇を離されると、ぼやけた視界の向こうに綺麗な地球が見える。 二つの星。水と空気に溢れる、奇跡のそれが。 少しだけ、細められて。 「 ・ ・ ・いけないことかい?」 「 ・ ・ ・ハ、 ・ ・ ・」 聞いたことも無いような、低い低い、大人の男の声。 きっと、昼間のままのソフィーであれば ・ ・ ・まず間違いなく既に逃げ出している。 今だって平気などではない。 現実に起こっていることなのかどうかすらあやふやなほどに、混乱しているのだ。 入浴前のハウルの雰囲気からはかけ離れているように思える。 それとも自分が只単に浅はかだっただけなのだろうか。 とにもかくにも冷静な判断ができず、ソフィーはひたすら躊躇い、戸惑う。 鼓動の音が、耳障りなまでに高鳴っている。 まともな返答など、できはしない。 けれどハウルはそれを恐らく見越した上で甘い行為に及んでくるのだ。 瞳が、見たことも無い光を称えている。 只々、美しく。 ・ ・ ・ふと。 先の花園での出来事が脳裏に浮かんだ。 彼の美しい双眸と、星の煌きに照らされた蒼さを帯びた夜空が似ていたのだ。 沸騰しかけていた思考をゆっくりと冷ますように、その不思議な回想はソフィーの中で巡っていく。自らの髪に未だに残る花々の香りと、あの泡沫のような言葉と共に。 ・ ・ ・そうだ。 ようやく、気がついた。 ハウルはこうしていつも、こちらに語りかけてくれていた。 なるべくこちらが困ってしまわないような道を探して。 それなのに、自分はどうであろう。 そんな彼の優しさにも気付かず、勝手に落ち込んだり勝手に戸惑うばかり。 そしてそんな自分の態度が、彼へと余計な心配をかけてしまう原因となった。 肝心なところで、まだ素直になりきれずにいた。 ハウルに嘘は吐かないといいながら、自らに嘘を吐き続けていたのだ。 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・あの ・ ・ ・ね、 ・ ・ ・ハウル ・ ・ ・ ・ ・ ・」 心のどこかで彼を加護しようと思い、またその想いが彼をまだ幼いと彼女自身を追い詰めてきたのかもしれない。 自分がしっかりしなければと、無理な背伸びをし続けてきたのだ。 一番幼かったのは、自分自身だったのに。 「 ・ ・ ・だ、いじょうぶよ ・ ・ ・ちょっと、びっくり ・ ・ ・しちゃった ・ ・ ・だけ」 「 ・ ・ ・大丈夫じゃないじゃないか」 ソフィーは苦笑した。 先ほどの彼からのキスで口内が痺れてしまい、上手く呂律が回らないのだ。 そんな理由を知らないハウルは、やはりまだ少年そのものなのだろうか。 けれどそれを自覚してしまった彼女は、また落ち着かない心地に襲われる。 妙な、不安と緊張と―――――目的の分からない、期待とに。 「夢、見てるみたいなの」 「 ・ ・ ・夢?」 自然と、そんな言葉がついて出た。 「雲の ・ ・ ・上を、 ・ ・ ・歩いてるみたい ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・雲の、上?」 ハウルが、そっとソフィーの手を取る。 「そう ・ ・ ・。 ・ ・ ・ふわふわ、するの ・ ・ ・」 「ふわふわ? ・ ・ ・なら、君と出会った時の僕と一緒だ」 ソフィーがハウルと出会った時とも、似ている。 彼に、恋に落ちる瞬間のあの時と同じ。 「くらくら、するわ」 「言われてみれば ・ ・ ・ああ、 ・ ・ ・僕もだ」 静かに囁く彼の瞳が、近づく。 「多分、僕の肺は壊れてる」 「 ・ ・ ・え?」 目の前に、在る。 「呼吸が上手くできないんだ」 「――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 少しだけ、荒い吐息。 ゆっくり、かすかに触れて首筋を滑る指。 「 ・ ・ ・君も、一緒みたいだね」 「 ・ ・ ・」 視界が、霞む。 意識はあるのに。 霧が掛かるように、現実味がない。 幻の中を踊っているかのよう。 彼の瞳がふと見上げた時の青空のように澄んでいて。 けれどそこには明らかに熱い太陽も存在していることを示していて。 それは、美しくも恐ろしい世界だった。 恐ろしいけれども、それ以上に惹かれる世界。 すさまじい引力に導かれ、ソフィーは抗わずにそれに屈する。 その先は、何も苛むことのない。 強力で謎に満ち溢れた残酷な魔法使いであり、優しく暖かな弱虫の恋人。 そして。 今夜としては、何度目かのキスを交わす。 特別でもない、ただ少しだけ触れ合わせるような優しいキスを。 やはり、二人は一般の恋人達とは思考が異なっているのだろうか。 ソフィーはハウルと結婚しても、ハウルはキスの”それ以上”を少しだけ覚えても、たったこれだけの軽いキスだけで満たされてしまうのだ。 それは決して愛が軽いというわけではなく。 今、こうして一つ屋根の下、一つのベッドの中、ふたりでいられるという日常そのものが、二人にとっては光り輝く奇跡そのもののように感じられるのだ。 ・ ・ ・幼少の頃にソフィーと出会い恋に落ち、ずっと彼女だけに恋焦がれ、ようやく再会を果たした矢先に戦争に巻き込まれ、それも落ち着きやっと二人で幸せになれると信じた途端 ・ ・ ・ソフィーは再びハウルの前から姿を消した。 何度も、何度も。 それも、つい先ほど起こった事のようなものだ。 恐怖は深く、深く、ハウルの中に強く根付いている。 それ以上の強い強い愛情がそれを後押しするのか、夜のハウルは甘えん坊に拍車が掛かる。 ・ ・ ・”魔法使いハウル”を知る者には到底想像もつかぬような彼の仕草や言葉は常にソフィーのみに注がれており、彼女もまたそれを不謹慎とは察しながらも、それだけ彼がこちらへと心を開いてくれているのだと思い、嬉しいと感じた。 今夜は仕事疲れも手伝って、いつも以上にハウルは甘えてくる。 ・ ・ ・否 ・ ・ ・甘え、というよりも――彼女に構ってもらおうと必死だ。 少しでも視線を逸らそうものなら、今にも泣き出してしまうかもしれないほどにだ。 冗談ではなく、これは本当の話である。 事実、彼は今にも泣きそうだ。 ・ ・ ・あのようなことが立て続けに起こったのだから、ハウルもまたソフィー同様疲弊してしまってもそれは当然ともいうべき現象だろう。 けれど―――今夜は、ハウルの様子が少しだけおかしい。 先ほどまで、あんなに大人の男性を見せ付けていたというのに。 ・ ・ ・まあ、それら全て正直なハウルは無意識のうちの行動なのであろうけれども。 赤子のように自分へとしがみ付いてくるハウルの背中にそっと腕を回しながら、ソフィーはくすくすと笑みをこぼし優しく問いかけた。 「どうしたの?ハウル」 「 ・ ・ ・ソフィー」 「なあに?」 どこまでも優しいソフィーの声と笑顔に、ハウルは眉を寄せ瞳を伏せる。
|
20050802
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
