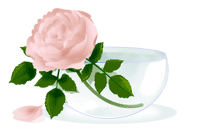
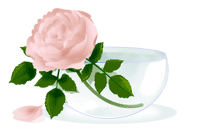
4
|
社交辞令の現場には慣れきってはいたものの、やはり居心地が良いとは言い難い。自立してから現在に至るまで、魔法使いとして生計を立ててはきたが ・ ・ ・
よもや、心を取り戻した副作用がここに現れるとは想定外のことだった。 帰宅してすぐ、ハウルはソファにドサリと脱力するように腰を下ろし、ありったけの溜息を吐く。久々にこんなまとまった仕事をしたためか、身体的にも精神的にも疲労困憊だ。身体に纏わりつく気だるさと、髪に絡みつく香水の匂いが忌まわしい。 時間は既に午後の11時を回っており、部屋は照明が落とされ薄暗く ・ ・ ・ それでも暖炉のカルシファーによる光と、テーブルの上のランプが灯されたまま煌々と静かに煌いていたため苦ではなかった。 城の住人は、もはや寝静まっていることであろう。 ハウルが気だるそうに長い金髪の前髪を指先で払うと、カルシファーがそっと薪から顔を出し、ハウルの顔色を確認すると軽く声をかけてくる。 いつもは何の気兼ねもなく言いたい放題な一面を除かせるカルシファーではあるが、何故かハウルが仕事から帰ってきたときだけは一人前に気を使ってみせる。 それは彼が魔の道に沈んでいく様を目の当りにしてきたからかもしれない。 魔法使いに対する依頼など様々ではあるが ・ ・ ・力があればあるほど、得体の知れない大きな何かとの繋がりが知らぬ間にできていることもある。 カルシファーは、それを懸念しているのだろう。 何より、ハウルの状態はソフィーの精神にも比例する。 逆もまた然り。 もはや、個人の問題などではないのだ。 「お疲れ」 そんな悪魔からの労いに、ハウルは静かに姿勢を正し、寝転んだが為に多少乱れた髪を手櫛で直しつつ苦笑として返事をしてみせた。 衣服に汚れや痛みもないし、怪我をしているようではない。 どうやらカルシファーが”懸念する”ほどの仕事でもないようだが―――。 ハウル自身、あまり良い状態ではなさそうなので、敢えてカルシファーは話題を摩り替えた。 ・ ・ ・その話題とやらも、下手をすれば彼の精神状態に害を為す可能性も ・ ・ ・多少は、無きにしもあらず ・ ・ ・なのではあるが。 「ちゃんと仕事してきたんだな」 「ん?」 「オイラはてっきり、どろどろに溶けて使い物にならなくなってるかと思ったぜ」 「 ・ ・ ・」 ハウルの微笑が消えた。 ・ ・ ・しかし、カルシファーは構わずに言いたいことをとにかく言い続けた。 これは長い間相棒として生きてきたカルシファーにしかできないことなのかもしれない。今ではソフィーも、すっかりその地位におさまりつつあるのだけれど。 「 ・ ・ ・あれからソフィーと話したか?」 「 ・ ・ ・いや? ・ ・ ・どちらにしても、午後から仕事の予定は入っていたからね」 地球色の瞳に、赤い火が僅かに揺れている。 ハウルは伏せ目がちに、男性特有の低い声で語った。 ソフィーは知らないが、普段の彼はこちらの声色の方が多いのだ。 どういうわけか、ハウルはソフィーの傍だとまるで子供に返ったかのように ・ ・ ・そう、少年そのものの声になってしまうのだ。 飾っているわけでも、演じているわけでもない。 どちらも本当の彼なのだ。 そんな、大人の男は再び綺麗な微笑を交え軽口を叩いてみせる。 「だけどカルシファー、そういう覗きは歓迎できないな」 どんな女性をも魅了しかねない男に、カルシファーは淡々と鋭い言葉を投げる。 「だったら自分の部屋とかでしてくれよ。ここはオイラの居場所だぜ!」 「 ・ ・ ・ふふっ ・ ・ ・、確かにそうだね。ごめん、忘れていたよ」 唯一の友人関係であるお互いは、やはりこうでなければならない。 どちらかが気を使うようになってしまったらもはやおしまいだ。 ・ ・ ・最も、そんなことなど、2人とも欠片も意識してはいないのだが。 「だけど、本当に良く落ち込まなかったな」 「 ・ ・ ・ん?」 「あんだけそっぽ向かれてさ」 重い腰を上げ、ハウルは上着を脱ぐと軽く畳んで腕にかける。 そうして瞳をそっと細め ・ ・ ・ まるで、呪文を紡ぐかのように言った。 視線は、小さな窓の向こうにある夜の街。 はるかな地平線を毅然と見据える鷲を思わせる瞳だ。 「 ・ ・ ・僕が僕を怖がってる」 「え?」 そっと瞳を細めて僅かな笑みを口元に浮かべたまま、ハウルはゆっくりとカルシファーへと視線を移す。 ・ ・ ・その表情は、何故か不思議な威圧感すら感じさせる。 さすが魔王の素質を秘めた男、ということなのだろうか。 けれど、その魔王になりかけた男は。 「僕が違う僕になっていく」 「 ・ ・ ・」 「ソフィーが言っていた通りだ。 ・ ・ ・心は、こんなにも重い」 「 ・ ・ ・ハウル」 カルシファーが初めてハウルに気遣わしげな視線を送ったことに彼は苦笑すると、おやすみ、という小さな一言を残していつものように淡々と二階にある自室へと帰った。 残されたカルシファーは、どことなくハウルが今感じている彼自身に対する恐怖というものの正体を感じ取り ・ ・ ・そっと、溜息を吐いた。 黒い煙が僅かにくすぶる。 思わせぶりなことをいうから、てっきりまた魔王への兆候が現れたのかと心配したのだが――― ・ ・ ・なんてことはない、その逆なのだ。 心を重いと言った彼は、明らかに魔の道から遠ざかっている証拠であろう。 「 ・ ・ ・ま、ソフィーが苦労することに変わりはないんだけどさ」 ・ ・ ・と。 まるで独り言のように呟くと、カルシファーは薪を抱え込み静かな眠りについた。 ――言われなかったが、とりあえず風呂に暖かいお湯を送ってやりながら。 自室の扉を開いた途端、目の前に飛び込んできたのは ・ ・ ・ 小さなテーブルに項垂れて、うたた寝をしているソフィーだった。 ハウルはてっきり、今日ソフィーはこの部屋にはいてくれないだろうと思い込んでいたのだから、驚くのも当然だろう。 ・ ・ ・彼自身、昼のことが引っかかって仕方がないのだから。カルシファーには別段その事に関しては語らなかった彼だが ・ ・ ・ 彼に指摘されたような事態にまではさすがにもうなりはしないものの、ソフィーに逃げられてしまったことと、自分が無意識のうちにしでかしてしまったことを思えば思うほど、胸が痛んで仕方がなかったり ・ ・ ・それでもどこか頭の奥がぼおっと心地よくぼやけているようで考えが上手くまとまらなかったり、とにかく混乱してしまうほどなのだ。 仕事をしているときも、そのことばかりが頭の中を駆け巡り ・ ・ ・恐らく覚えてはいないが、貴婦人への対応もぞんざいで愛想のないものであったに違いない。 自分の容姿に対する自覚が無いわけではないため、どこにいっても女性に群がれるのは自業自得だとはいえるのだけれども ・ ・ ・ 自分が容姿を磨くのは、ソフィーのためなのだ。 彼女の夫として恥ずかしく無いような男になるためにはどうすればいいのかと彼なりに考え、行き着いた答えが”できることから無理なくする” ・ ・ ・ということであった。 結果、一番楽な”容姿”をまず最初に選んだことが、言ってしまえば自分らしいといえば自分らしい――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ああ、違う。 また考えがおかしな方向へと飛んでいってしまったではないか。 ソフィーはまだ、あの蒼いドレスを纏ったままである。 つまり彼女は彼の帰りを風呂にも入らずずっとこうして待っていてくれたのだ。 きっと、沢山色々考え込んで、悩んで、辛い思いをしたに違いないであろうに。 逃げずに、受け止めようとしてくれたのだ。 何より、この部屋にいてくれたことが一番嬉しかった。 今日はもう顔を見ることができないだろうと諦めていたのだから。 起こすのも躊躇ったが、このままここで眠らせておくわけにはいかないし、入浴もまだ済ませていないのだろうから ・ ・ ・と、細くて小さな肩にそっと手を掛け、耳元に唇を寄せてそっと囁く。下手にゆすったり大声を出したら驚かせてしまうだろうとの配慮だ。 「ソフィー」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 「ソフィー、起きて」 「 ・ ・ ・、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ん ・ ・ ・ ・ ・ ・」 「ソフィー」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ん ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・ハウル ・ ・ ・ ・ ・ ・?」 こんな小さな声で起きてしまうのだから、浅い眠りだったのだろう。 小さな瞼がそっと開かれ、茶色の瞳がそっとその姿を現した。 ・ ・ ・けれど、それはあっというまに覚醒をして。 ソフィーは勢い良く飛び起きた。 「 ・ ・ ・やだ、私ったら!すっかり眠っちゃって ・ ・ ・、ごめんなさい、みっともないわ ・ ・ ・!」 と、髪を手櫛で忙しなく整え、あたりを見渡し時計を見て驚愕し、そして更に焦りだすソフィーにハウルは半ば呆気にとられる。 ・ ・ ・想像していた反応と全く違っていたからだ。 あんなことの後に一度も顔を合わせていなかったものだから、彼の中で悪い想像だけが頭に過ぎり続けていたことによる反動なのかもしれないが。 起こしたらすぐに謝ろうと思っていたのに、逆に謝られてしまった。 故に、ハウルは完全に言葉を失ったのだ。 けれど、ソフィーはまたせっせと働こうとするのだ。 もう、こんな時間であるというのに。 「あ、お腹空いてる?ご飯はもう済ませたのかしら」 「え ・ ・ ・」 「ちゃんと聞いておかなくてごめんなさい。だけどもしかしたらと思って」 「いや、仕事先で済ませてきた。 ・ ・ ・それにもうこんな時間だしね」 「 ・ ・ ・そうね。それじゃあお風呂に入ってきたら? ・ ・ ・酷い匂いよ」 「ん ・ ・ ・」 ソフィーはこの匂いが女性用の高級な香水によるものだと知っているのだろう。 困ったように微笑んで指摘されたが、変な誤解をされても困る。 頭の良い彼女であること ・ ・ ・否、おそらく自分のことを一番理解してくれているであろうが―――ハウルはとりあえず、自分の仕事内容を報告することにした。 優しい彼女は、自分から言わない限り聞いてこないような気がする。 ・ ・ ・いや ・ ・ ・自分には聞かずにカルシファーあたりにでも聞くのだろうか。 それも何処か悔しい気がする。 「 ・ ・ ・僕がこの前いった所属先覚えてる?」 「 ・ ・ ・ええ。魔法使いに”正しい”仕事を与えてくれる機関ね」 「そう。 ・ ・ ・その仕事っていうのがさぁ ・ ・ ・貴族が主催するパーティーの警備なんだよ」 「警備 ・ ・ ・」 瞬間、ソフィーの表情が曇ったことをハウルは見逃さなかった。 それでは結局下手をすれば傷ついてしまうことと同じではないか ・ ・ ・と不安になったのだろう。 ・ ・ ・けれども。 「大丈夫。ソフィーが心配することなんて何一つありはしないさ」 「でも ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・王室はともかく、何の力も持たない金持ちだけの集まりさ。来るとしても盗賊かごろつきか ・ ・ ・いずれにしても”魔法使い”の相手にはならないさ」 ・ ・ ・別に自惚れているわけではない。本当の話なのだ。 どんなに下級の魔法使いでも、その気になれば人を一人呪い殺すことなど容易い。それは一般の人間が剣と銃を丸腰の人々に向けることと同等なのである。 故に、魔法使いは国際的に保護されつつあるのだ。 加害者にも、被害者にもさせないために。 「屋敷の四方八方に結界を張って、パーティーが終わるまで会場の隅っこに座っていればいいだけの仕事さ。 ・ ・ ・ああ、でもさぁ、なんでエラいヒトって長話好きなんだろうねぇ。座り続けて何だか疲れたよ」 ・ ・ ・と、どさくさに紛れて脱力するふりをしながらソフィーの肩にもたれかかる。 ほとんど、抱き寄せている格好だ。 我ながら子供のようなことをしているとは思うのだが、仕事をしている際もあれやこれやと昼間のことで延々と悩みつつも、ソフィーへの禁断症状のようなものが現れて仕方が無かったのだ。 ソフィーの顔が見たくて、ソフィーと話をしたくて、ソフィーに触れたくて仕方が無かった。あれほどの酷い事件に遭遇した矢先ということと、結婚後ずっと傍にいたためか、離れることに慣れていなかったことが重なったのだろうか。 ・ ・ ・理由は、本当はどうでもよいのだけれど。 ソフィーはそんなハウルを拒絶することなく、けれども実に彼女らしいお説教をさりげなくこの甘え上手な魔法使いに浴びせるのだ。 「それも立派なお仕事の一つよ。沢山のお金を貰っているんですもの。文句を言ってはいけないわ」 ・ ・ ・本当、ソフィーらしいや。 ハウルは彼女の肩に顔を埋めたまま、くすくすと笑い出す。 それにソフィーは怪訝な顔をしていたものだが、大体予想はついたのか、これといった反論は一切せずに今の状態に甘んじた。 背中に、優しい感覚が走る。 ・ ・ ・ソフィーが背中に手をそっと回してきたのだ。 あのような”現場”を目の当りにした直後、ソフィーの慎ましさは心に響く。 冗談などではなく、この部屋に入った直後にソフィーの寝顔を見たとき神様かとすら思えたほどなのだ。 ・ ・ ・気付いたときには、思っていたことを素直にソフィーへと伝えていた。 「 ・ ・ ・世の中ってさ、思っていたより過酷だね」 「え?」 「夫婦で参加してるひとがほとんどだったんだけど ・ ・ ・旦那さんが見てるって分かった上で若い男を引っ掛けようとしてるひとばかり」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・あなたも?」 「まあね ・ ・ ・蟻にたかられる飴の気分だったさ」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・それでこの匂い ・ ・ ・」 「ごめん ・ ・ ・気になるよね。僕も嫌いだ、こんな匂い」 ソフィーから身体を離して、背後のベッドにそのまま仰向けにドサリと倒れる。 少しだけベッドにいつもの香りを感じて安堵した。 彼女はそのままの位置で、そっとハウルを見つめている。 「でも僕は大丈夫だった。ソフィーが守ってくれたから」 「 ・ ・ ・えっ?」 「これ」 「 ・ ・ ・あ ・ ・ ・」 寝転んだまま、彼は左手を彼女へと差し出してみせる。 ・ ・ ・言われなくてもハウルが何を言いたいのかが分かった。 「さすがに、既婚者には手を出せないんだろうね。 ・ ・ ・けど僕が見た限り、何人かは断れなかったのか自ら望んで行ったのか ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・」 「ま、僕は手を出される前に追っ払うか牽制するけどね。今日はどうやら、僕の奥さん自慢が利いたみたいだけど」 「 ・ ・ ・? ・ ・ ・なあにそれ?」 「あそこの料理、マズかった〜」 「 ・ ・ ・」 ・ ・ ・と。 またしてもソフィーはハウルに会話を”勝手に自己完結”されてしまったのだが ・ ・ ・ 何故か、悪い気はしなかった。 ・ ・ ・分かっているのだ。 彼は――――相当疲れている。 「明日もお仕事あるの?」 「 ・ ・ ・ううん、今日のだけでまとまった依頼料は稼げたから。当分は」 「分かったわ。 ・ ・ ・さ、そのまま寝てしまってはダメ!ちゃんとお風呂に入らなきゃ疲れがとれないわ。ほら、起きて」 「眠い ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・今日、お花畑のハーブを使って入浴剤作ってみたの。お風呂場に置いてあるから良かったら使っ ・ ・ ・」 「え、本当?楽しみ!」 ソフィーが言い終えぬ間にハウルは飛び起き、笑顔で子供のように言う。 毎度の事ながら、態度がころころ変わるので目まぐるしい。 ・ ・ ・それが彼の短所なのであるが ・ ・ ・それもまた彼らしく嫌いではない。 などと、思っていると。 風呂場へ向かおうと部屋を出ようとしていたハウルがこちらを振り向いたので驚く。 着替えなら用意してあるわよ、とソフィーは思わず反射的に答えようと口を開きかけたのだが ・ ・ ・ 「ソフィーもまだ入ってないよね。お先にどうぞ?」 「えっ ・ ・ ・」 ・ ・ ・ある意味、恐れていた一言であった。 「い、いいわ ・ ・ ・ハウルが先に入って」 「僕、今夜は長湯しそうだから。ソフィーが先のほうがいいよ」 「あ、でも ・ ・ ・、私今日はお風呂に入れないから ・ ・ ・」 「?どうして?」 「 ・ ・ ・どうしてって ・ ・ ・」 口元を恥ずかしそうにそっと押さえながら、わずかに顔を赤らめながら下を向いてしまったソフィーを見て ・ ・ ・ハウルは何かを察したのか、あ、と声を漏らす。 いくら彼でも、女性特有の月の事情くらいの知識はある。 ・ ・ ・とは言え、魔法学校では、女性の場合大きく魔力が偏る週間だということで教わっただけなのだが。あくまでそういう知識としての範囲だった。 しかしハウルの場合、幼い頃にある程度の教育を叔父から受けていたため、”正しい一般的な意味”としてしっかりと把握していた。 そうか、だから今朝具合が悪そうだったのか ・ ・ ・と脳裏で納得するが ・ ・ ・ それにしても ・ ・ ・野暮なことを聞いてしまったと今更後悔する。 けれどここで謝罪するのもどこかおかしいような気がする。 この話題は軽く打ち切った方がいいだろう。 「そっか。 ・ ・ ・それじゃ、お先に」 「 ・ ・ ・うん」 ハウルはそっと微笑んで、ソフィーの頬にキスをする。 ある意味彼のこの対応は、彼女を大いに安堵させるものだった。 「ハウル、お仕事お疲れ様。 ・ ・ ・ありがとう」 柔らかな笑顔で、ソフィーはそっとハウルの両手を己の両手で包み込み、祈るように瞳を伏せて言う。 自分が働くことによって、”ありがとう”なんて言われたのは初めての経験だった。 同時に、どこか胸に安堵のような、重い枷が取れたような感覚を覚えたが ・ ・ ・ なんてことはない、きっとソフィーからの言葉が、自分は嬉しかったのだ。 ソフィーと城に暮らし始めてからの、初めての仕事だった。 この世界の魔法使いは国を問わず国際的な機関によって統制されている。 それはきわめて平和主義な連合であり、魔法を戦争やテロ、あらゆる暴力的なものに使用することを固く禁じるために世界で作られた機関だ。 キングズベリーと隣国である国は戦時中であるため、その連合からは脱退したのだが、ハウルはどちらの国にも属さず、今では自衛のためだけにその力を使っている。 その為彼は連合から認められ、連合に属し、連合から定期的に与えられた仕事をこなす立場となったのだ。 故に仕事の内容はしっかりと管理されたもので、実に働きやすい内容だった。 いわば、契約社員のようなものだろう。 一見不安定な収入のように思われがちだが、ハウルほどの魔法使いを半日拘束するだけでも恐ろしい額になるのだ。 それは、魔法というものが強大なものであることの表れなのだ。 単純に言ってしまえば、今回の収入であと三ヶ月は働かなくても済むのだ。 ちなみに、城の金銭面の管理は全てソフィーに任せている。 さすが若くして帽子屋を切り盛りしてきた少女である。 最初は城の財産額に目を丸くしていたものだが、それもつかの間、てきぱきと整え、無駄な出費は一切なくなるまでになった。 マルクルが生まれて初めて”お小遣い”なるものを貰い、それはもうはしゃぎにはしゃいでいた光景は記憶に新しい。 今まではマルクルに預けていたため、律儀な彼は自分のための金を用意することがなかなかできずにいたらしい。心のなかったハウルは、適当に等分し、単純にそれをマルクルに渡していただけなのだから。 しかもそれは、あくまで生活費としてだけだった。 駄目な大人の見本のようだ ・ ・ ・と、今更のようにハウルが自覚すると同時に、ソフィーは夜ということもあるのかいつもより声量を抑えた落ち着いた声で言う。 いつになく、静かな瞳だった。 ・ ・ ・初めて見るような気がする。 「 ・ ・ ・ね、ハウル」 「ん?」 「さっきの、ご婦人のお話だけど ・ ・ ・」 「 ・ ・ ・うん?」 ハウルはもうその話題は終わったものだとばかり思っていたので、ソフィーのこの言葉には多少驚かされた。彼女は思ってもみないところで、提供される話や物語を深く受け止めている節がある。 有名でありふれた御伽噺ですら、ソフィーの見解を聞いてみれば実に斬新で面白く思えるのだ。そう言うと彼女は”父の受け売り”と笑って受け流すのだけれど。 そんな彼女は、突然こんなことを言い出すのだ。 「 ・ ・ ・きっと、旦那さまに見てほしかったのね」 「 ・ ・ ・」 「だから敢えて目の前でやったんだわ」 まさか、肯定するとは思ってもみなかったのだが―――― 「 ・ ・ ・それが裏切りだと分かっていても?」 「その前に裏切られたのかもしれないわ」 「 ・ ・ ・」 ・ ・ ・言われてみれば。 あの貴族の傍らには異なる女性の姿を見たような気がする。 「私はとっても幸せだから ・ ・ ・こんなことを勘ぐるのは間違いだけど ・ ・ ・」 ソフィーは身に着けたままだったエプロンをゆっくりと外しながら、囁くように言う。 「愛していなければ、奥さんにはなれないわ」 「 ・ ・ ・」 「愛しているから奥さんになって、愛しているから一生懸命頑張って ・ ・ ・でも」 「 ・ ・ ・でも?」 いつになく、ハウルの声は薄暗い部屋に低く響く。 地球色の双眸が、ランプの光に反射して揺らめいて見える。 それを受け止めて、ソフィーはいつもの穏やかな眼差しで笑みすら浮かべて言う。 大袈裟、というわけではなく。 本当に、聖母のような微笑だった。 ・ ・ ・けれど。 「いつまでも、ぎざみみハーゼを守るお母さんではいられないのよ」 「 ・ ・ ・え?」 「心の底ではね、奥さんじゃなくて恋人でいたいって ・ ・ ・思ってるのかもしれない」 「――――――― ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・」 彼女は、その枠に嵌められてしまうことを拒むのだ。 聖母の笑みが ・ ・ ・突然、全く違う色へと変わる。 万華鏡のように、目まぐるしく。 「私は貴族じゃないし、貴婦人の生活なんて想像もできないけど ・ ・ ・」 そして巡って ・ ・ ・いつもの優しい、ソフィーらしい笑顔を見せる。 外したばかりのエプロンを遠慮がちにハウルへと見せながら。 「私だってエプロンを外しちゃったら、ただの女の子に戻るもの」 「 ・ ・ ・」 「そのひとも、きっと私とあまり変わらないのかもしれないわ」 同じ、女性だから。 ただただ、愛してほしい気持ちだって種類は違っても源は一緒だから ・ ・ ・と。 「 ・ ・ ・でも、裏切ることはいけないことね」 「 ・ ・ ・」 そして、最後には正論で会話を完結させる。 「それに私は、あなたになら ・ ・ ・ぎざみみハーゼのお母さんになってもいいわ」 「 ・ ・ ・」 「例えそうなってしまったとしても、ね」 「 ・ ・ ・ソフィー」 ”ぎざみみハーゼ”。 ハウルも、遠い昔にどこかで聞いたことのある言葉だった。 幼い頃に読んだ、絵本だったような気がする。 けれど悲しいかな、どんなに夢中になった絵本でも、大好きだった歌でも、大人になっていけばいくほど自然とそれらは記憶の中で風化してしまう。 どんなに探っても探っても、もう思い出すこともできない。 けれど ・ ・ ・ その中の、一場面だけが何故か突如として鮮明に蘇る。 母からの愛に無縁だった幼い頃の自分にとっては衝撃的に感じたのだろう。 脳裏に焼きついて離れない”ぎざみみハーゼ”の最後の場面。 ・ ・ ・刹那。 ゆったりと、穏やかに語るソフィーの中に明らかなる強さと覚悟をどこかで感じ取り、とたんにハウルは不安になった。 その気持ちを抑えることができず、思わずソフィーを抱きしめる。 彼女の、息を呑む音が耳に届いたが、構ってなどいられなかった。 ・ ・ ・花畑に長い間いたのだろうか。 彼女の星色の髪は、花の香りに染まっていた。 心地よく、鼻をくすぐる。 そんなハウルとは異なり、ソフィーは腕の中でうろたえた。 力が思いのほか強く、彼の胸に抑えつけられるような形になって息もつかない。 自分の言葉がここまで彼に影響してしまうとは想わなかったのだ。 「ハウル ・ ・ ・?どうしたの? ・ ・ ・苦しいわ」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ごめん」 そういいながらも、彼は一向に力を弱めることはしなかった。 思わずソフィーは身じろぎする。 けれど微動だにすることすら許さぬように、彼はただただ彼女を拘束する。 ハウルの想いを全く知らないソフィーは、ただただ困惑する。 小さく震える彼女に、ハウルは一見、見当違いとも思える言葉を紡いだ。 ソフィーからすれば、予想範囲外の言葉であったに違いない。 「今度港町に行くときは、僕に声をかけて」 「 ・ ・ ・どうして?」 「今日仕事で話題に上がってた。 ・ ・ ・最近敗戦の噂が国中に流れて兵士達が混乱してる。 ・ ・ ・若い女性が何人も犠牲になったらしい。港町には酒場が多いから、泥酔した兵士達で路地中埋め尽くされてる」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・」 敗戦するということは、敵国の条件によっては直接兵士達の生死に関わる。 彼らはそれを恐れて、こわくてこわくて仕方がなく酒にすがるしかないのだろう。 けれど ・ ・ ・だからといって、許されることではない。 「君はとても綺麗だから ・ ・ ・絶対最初に狙われる」 「 ・ ・ ・大丈夫よ、私綺麗でもないし、地味だから目立たな ・ ・ ・」 「言うことを聞きなさい」 「っ ・ ・ ・」 小さな顎の先を、繊細な指先が捉えて上を向かされる。 恐ろしいほどに真剣な彼の双眸とぶつかり、ソフィーは言葉をなくした。 「 ・ ・ ・確かに僕は、ぎざみみハーゼそのものかもしれない」 「 ・ ・ ・ハ ・ ・ ・」 「だけど君は、母さんハーゼになる必要はないんだ」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・、 ・ ・ ・ハウル ・ ・ ・」 父親が、駄々をこねる幼い娘に言い聞かせるような声と言葉だった。 優しさと、厳しさが混じるときっとこういう声になるのだろう。 戦争は、命を蝕み、次第に人々の心をも破壊していく。 人が人の道を外し、弱者はそれらの犠牲となる。 年端もいかない少女も、無邪気な少年も、乳飲み子も、老人も。 ハウルは、いやというほどその現場をその目に焼き付けてきた。 慕っていた肉親の変わり果てた亡骸を、恐怖のあまり葬ることすらできなかった。 その悲しみが、彼に戦時中の国家から独立させる強さと、わずかなことで脆くも傷ついてしまう繊細な弱さを与えたのだ。 ハウルは、ソフィーの頬をそっと優しく撫でて ・ ・ ・ようやく、微笑んだ。 「明日から嫌がらせみたいにベタベタしてあげるよ」 「 ・ ・ ・えっ?」 「馬鹿じゃないかって言われるくらいにね」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・」 「今日、いやというほどそういう男女を見せ付けられてきたからね。ある意味勉強にもなったよ」 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・はっ?」 「とりあえず、参考までに」 ”大人の笑み”と共に、そう言い残して。 彼はさっさと風呂場へと行ってしまった。 後に残されたソフィーは、ただ呆然と彼が出て行った扉をずっと見つめていた。 真っ赤に染まった両頬を押さえ、思わずその場に座り込んでしまいながら。 うらはらに、頭の中では彼の発した様々な言葉が目まぐるしく回り続けていた。 心が、しびれている。 しばらくの間、ソフィーはその場から動けなかった。 膝の上の外したエプロンをそっと手繰り寄せるように抱きしめて。 どんなにキツい香水に塗れても、それらに染まることの無い彼がもつ香りが確かに自分の髪にわずかだけれども移っていて。 胸が、高鳴る。 こんなことでこれだけのことになってしまって、これから先、自分は本当に大丈夫なのだろうか ・ ・ ・と、いささか妙なことを心配しながら。 |
20050627
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
